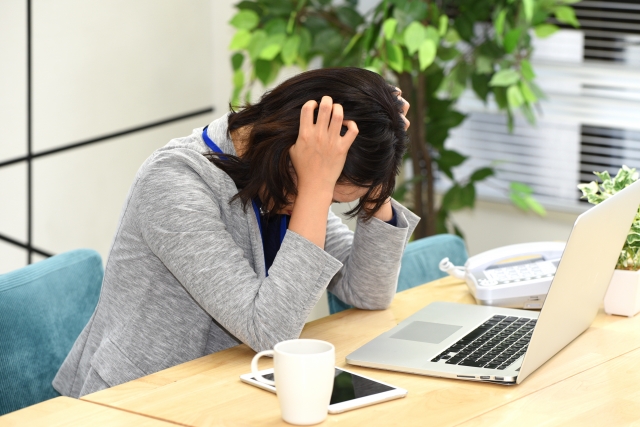ハラスメント
セクハラに遭った際の相談の流れや注意点を弁護士が解説!

1.セクハラとは
そもそもセクハラとは何でしょうか。セクハラとは「セクシャル・ハラスメント」の略で、ハラスメントの一種です。
厚生労働省の「職場におけるハラスメント対策マニュアル」によれば、「職場における性的な言動に対する他の従業員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の従業員の就業環境を害することをいう」とされています。
セクハラというと、男性から女性に対する行為や発言を思い浮かべる方が多いと思いますが、必ずしも男性から女性に対する行為や発言に限られません。女性から男性に対する行為や発言についてもセクハラとなる可能性はあります。
例えば、上司が部下に対し「今度ホテルに行こうよ」と発言した場合、誰が聞いてもセクハラ発言であることは明らかです。しかし、一般的にどのような発言がセクハラ発言に当たるのか、微妙な場合も多いです。以下では、セクハラ発言に当たり得る例をご紹介します。
例1:しつこく食事に誘う
職場で上司が部下をランチに誘う光景は一般的にみられることです。それ自体はセクハラ発言に当たりませんが、特定の人をしつこく誘ったりすると、セクハラ発言に当たる可能性があります。
例2:性的なうわさ話
「あいつは〇〇と浮気しているらしい」といった言動は、飲み会などの場でつい言ってしまいがちですが、性的なうわさが社内に流れてしまうと不利益を与えることになることから、セクハラ発言に当たり得ます。
例3:性的な部分をほめる
「きれいだね」「スタイルいいね」といった言動は、相手をほめる発言であることから、一見問題なさそうに見えます。しかし、こういった発言は、言われた相手が不快に思うこともあります。よって、ほめる発言だから問題ないだろうと思わず、相手が不快に思うか考えるようにしましょう。
2.セクハラ相談の流れと注意点
次に、セクハラを受けた場合の相談の流れと注意点について解説します。
2-1.セクハラを受けた場合の相談の流れ
セクハラを受けた場合、どこに相談したらよいかわからない方も多いでしょう。特に、職場の上司からセクハラを受けている場合、上司に相談するわけにはいきません。また、センシティブな内容ですから、同僚に気軽に相談するわけにもいかない場合が多いと思います。
セクハラの相談窓口としては、大きく分けて社内窓口と社外窓口があります。
社内窓口としてまず考えられるのは、人事部です。人事部は、社内の人的トラブルの相談窓口になっていることも多いため、まずは人事部に相談してみるのがよいでしょう。人事部であれば、セクハラをしている社員に対して指導がしやすいですし、早期の解決がしやすいというメリットがあります。
また、昨今のコンプライアンス遵守の風潮から、社内に通報窓口を設けている会社もあります。そういった会社の場合、通報窓口に相談するのもよいでしょう。セクハラはセンシティブな悩みですから、プライバシーが守られる通報窓口は相談者にとって安心感を与えます。通報窓口は、上司や人事部へ情報が行かない仕組みとなっていることがほとんどなので、会社に知られたくないと考えている方にとっては安心できる相談窓口です。
次に、社外窓口は、社内窓口では解決できなかった場合に相談する場合が多いと思います。社外窓口としては、例えば労働環境均等部があります。労働環境均等部は、労働局が管轄している相談窓口で、男女雇用機会均等法に関わるトラブルの相談を受け付けており、セクハラももちろん相談できます。
セクハラに関して損害賠償などの法的な措置を検討している人は、弁護士に相談するのがよいでしょう。弁護士であればセクハラに関する法的な解決手段を提案してくれますし、代理人として会社に対する交渉や労働審判を行ってくれますから、非常に心強い味方となってくれるでしょう。
2-2.相談の注意点
社内窓口に相談する場合、相談した日や相談した内容の記録が残る手段で相談してください。後々裁判や労働審判になった場合、証拠を提出する必要があります。記録が残っていないと証拠として提出することができず、不利になってしまうかもしれません。社内窓口にいつどのような内容を相談したのか、記録が残る電子メールなどで相談するようにしましょう。
3.セクハラ被害を受けた場合の対応方法
セクハラ被害を受けた場合、社内外の窓口に相談することをお伝えしました。社内窓口であれば、社内で解決を図ることもできるでしょう。一方で、会社に相談しても取り合ってもらえない場合もあります。会社側がセクハラの加害者である上司に配慮したり、会社の評判が下がることをおそれて問題として取り上げないという可能性も否定できないからです。
その場合、社外窓口に相談することを検討します。労働環境均等部への相談や、弁護士への相談を検討しましょう。社外窓口に相談することで、会社に対する対応方法を検討することができます。
以下では、セクハラ被害を受けた場合の対応方法について具体的に解説します。
3-1.セクハラ被害を受けた場合の心理的ダメージに対する対応方法
セクハラ被害を受けた場合、精神的な苦痛を伴うことが多いと思います。精神的な苦痛に対しては、損害賠償請求をすることになるでしょう。損害賠償請求をするためには、弁護士に相談する必要があります。社内窓口に相談しても、損害の賠償をしてくれるわけではありません。心理的ダメージに対する金銭的な法的措置を取ることができるのは弁護士だけです。金銭的な被害回復を望んでいる人は、弁護士に相談するようにしましょう。
3-2.セクハラ被害の対応に際しての注意点
セクハラ被害に対応するための注意点は大きく分けて2つあります。以下では、その2つを詳しく解説します。
(1)セクハラの経緯をまとめる
セクハラ被害を受けた人にとって、セクハラ被害を思い出すのはつらいと思います。できれば忘れたいですし、記録にも残したくないと思いますが、弁護士に相談するためにはセクハラの経緯をまとめることが必要です。
弁護士は、相談者から相談を受けた際、まずは事実関係を詳細にヒアリングします。その際に経緯がまとめられていないと、適切なアドバイスができない可能性があります。よって、セクハラの経緯をまとめておくことが重要です。セクハラ被害により精神的なショックを受け、うまく話すことができない場合も多いため、落ち着いてまとめられるときに以下のことを中心にまとめておくことをおすすめします。
- セクハラ被害が始まった時期、頻度
- セクハラの加害者、態様
- セクハラ被害について会社に相談したときの時期、内容
- セクハラ被害で通院をしたことがある場合はその時期、診断結果
(2)セクハラの証拠を収集する
セクハラ被害があったと会社に対し主張しても、証拠がなければ事実かどうかを確認することができず、有利に交渉を進めることができません。
後に労働審判や裁判になった場合には、セクハラ被害の証拠を提出する必要があります。よって、セクハラ被害があったらなるべく詳細に証拠を収集しておく必要があります。
具体的にどのように証拠を収集するかですが、例えば以下のような証拠を収集しておくのが望ましいでしょう。
- セクハラ発言をされたときの発言を録音又は録画したもの
- セクハラ発言をされたメールやLINEなどのメッセージ
- セクハラ被害について会社に相談したときのメール
- セクハラ被害を受けたことを記録したメモや日記
- セクハラ被害で通院をしたことがある場合はその日付と診断書
4.セクハラ問題の法的手続
セクハラ被害を弁護士に相談した場合、最終的には法的措置を検討することになるでしょう。セクハラ被害に対する法的措置は、大きく分けて労働審判と訴訟があります。以下では、法的措置の一つである労働審判について詳しく解説します。
4-1.労働審判とは
そもそも労働審判とはどういった制度なのでしょうか。労働審判は平成18年4月から開始された制度で、労働者と会社との間で発生した労働に関するトラブルを迅速に解決するための手続です。セクハラのほか、未払い残業代や解雇などの労働トラブル全般を解決することを目的としています。
トラブル解決手段としては、訴訟が思い浮かぶと思います。しかし、訴訟は結果が出るまで1年以上かかることも珍しくありません。迅速に解決するためには、労働審判を活用することをおすすめします。なぜなら、労働審判は訴訟と異なり、原則として3回以内の期日で終了するとされているからです。労働審判は通常3か月以内に終了することが多く、裁判と比較して迅速な解決を目指すことができます。
4-2.労働審判の注意点
労働審判は労働者と会社との間で発生した労働に関するトラブルを解決するためのものですから、セクハラをした加害者個人に対して労働審判を起こすことはできません。セクハラをした加害者個人に対する損害賠償請求などは、訴訟を起こす必要があります。
では、セクハラ被害については労働審判を利用できないかというと、そうではありません。会社には「安全配慮義務」という義務があり、従業員がセクハラのない環境で仕事ができるよう配慮する義務を負います。この義務に対する違反があったとして会社に対し労働審判を申し立てることは可能です。あるいは、会社は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」(いわゆる「使用者責任」。民法715条)ため、セクハラ被害が「事業の執行について」行われた場合には、会社に対し、労働審判を申し立てることができます。
4-3.労働審判の手続の流れ
(1)申立書の提出
労働審判を行うためにはまず、トラブルを管轄する地方裁判所に対し労働審判申立書を提出します。労働審判法5条によれば、申立書には、以下の事項を記載しなければならないとされています。
- 当事者及び法定代理人
- 申立ての趣旨及び理由
(2)期日の指定
申立書を提出すると、裁判所から第1回労働審判期日の指定及び呼び出しがあります。第1回期日は、原則として申立てから40日以内に設定するとされています。
(3)第1回労働審判期日
労働審判は、裁判官から指定された労働審判官1人と、労働審判員2人で組織する労働審判委員会にて手続が行われます。労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者から任命されます。
第1回期日では主張の整理と証拠調べが行われ、大方の心証が形成されます。
(4)第2回労働審判期日
第2回期日は、第1回期日から2週間~1か月後に設定されます。第2回期日では、第1回期日で確認できなかった事実関係の確認や証拠調べをすることもありますが、第1回期日で終了している場合がほとんどです。そのため、第2回期日ではお互いの主張を踏まえた調停が行われることが通常です。
統計上、約7割の審判は第2回期日までで審理が終了しています。
(5)第3回労働審判期日
第1回及び第2回の調停で話し合いでの解決が難航した場合、第3回期日が開かれます。引き続き調停での解決を目指すために話し合いが行われます。
(6)労働審判の終了
労働審判の終了の仕方には「調停成立」と「審判」の2種類があります。「調停成立」とは、話し合いがまとまったときに成立するもので、話し合いにより解決した内容の調書が作成されます。調停は、裁判上の和解と同一の効力を有しますので、法的な効力を有します。話し合いによる柔軟な解決方法を記載することができるため、できる限り調停でまとまるのが望ましいといえるでしょう。
仮に話し合いがまとまらなかった場合、「審判」が下されます。審判の内容に異議がある場合、異議申立てを行うことができます。異議申立てがあると審判は効力を失い、通常の訴訟手続へ移行します。その後は訴訟手続において争いが継続します。
4-4.労働審判での証拠提出の仕方と注意点
先に述べたように、労働審判は、原則3回以内の期日で終了します。審判官や労働審判員は、第1回期日で大方の心証を決めると言われています。よって、3回期日があると思わず、第1回期日で重要な証拠はすべて提出する必要があります。なお、第2回期日終了後の追加証拠の提出は原則として認められません。審判官や労働審判員に有利な心証を形成してもらうために、第1回期日で提出できる証拠はすべて提出するようにしましょう。
5.弁護士への依頼
セクハラ被害を受けた場合、被害者自身が会社と交渉をしたり労働審判を申し立てることは可能です。しかしながら、セクハラ被害を受けて精神的なダメージが大きい中で会社と交渉をしたり労働審判に出席することは多大な労力を要します。セクハラ被害に対する法的措置を検討している場合、弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
以下では、弁護士に相談するメリット、弁護士ができる対応内容、弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用について解説します。
5-1.弁護士に相談するメリット
弁護士に相談を行うメリットは大きく分けて3つあります。
まず一つ目のメリットは、多くの証拠が収集可能である点です。セクハラ被害に対する法的措置を取るためには、セクハラ被害があったことを立証する証拠の存在が重要になってきます。
弁護士に相談すれば、トラブルの当初から適切な証拠を収集することが可能です。法律の専門家である弁護士は、裁判や審判で有利になり得るかを考慮しつつ、証拠収集について依頼者に適切なアドバイスをします。よって、依頼者自らが証拠を収集するよりも適切な証拠を多く収集できる可能性が高まるというメリットがあります。
二つ目のメリットは、交渉や審判の矢面に立つ必要がなくなる点です。弁護士を代理人に立てて交渉を行えば、自ら矢面に立つことなく交渉ができるため、精神的な負担から解放されます。セクハラ被害を受けている被害者にとって、会社を相手に交渉や審判を行うことは多大な心痛を伴うことから、弁護士が全て代理してくれるメリットは大きいといえるでしょう。
三つ目のメリットは、法的に不利にならない点です。労働問題に精通した弁護士に依頼すれば、過去の裁判例や労働審判をもとに、法的に有利な主張を組み立ててくれます。よって、自分で交渉を行うよりも有利といえるでしょう。
5-2.弁護士ができる対応内容
弁護士は、労働問題に関するすべての法的な手続を代理することが可能です。よって、会社との交渉はもちろん、労働審判や訴訟についてもすべて対応することができます。セクハラ被害を受けた被害者にとって、精神的なダメージが大きい中で慣れない交渉や労働審判を行うことは負担が大きいです。その負担をすべて代理してくれる弁護士は心強い味方となるでしょう。弁護士ができる具体的な内容は以下のとおりです。
- セクハラ被害についての法律相談
- 会社との交渉、和解契約の締結
- 労働審判の申立て
- 訴訟提起
- 刑事告訴
5-3.弁護士費用
弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。弁護士費用は大きく分けて着手金と報酬金の2つがあります。以下では、セクハラ被害について弁護士に依頼する際の費用を具体的に解説します。
(1)法律相談料
弁護士に相談する場合、着手する前の相談料として、およそ30分5,000円の相談料がかかります。なお、事件の依頼を受けることを前提に、法律相談料を無料としている法律事務所もありますので、確認してみるとよいでしょう。
(2)着手金
着手金とは、事件に着手する際に弁護士に対して支払う費用のことで、事件が依頼者の希望通りに解決しなかったとしても戻ってこない性質の費用です。着手金の相場は以下のとおりです。
- 会社との交渉 10万円~20万円前後
- 労働審判の申立て 10万円~30万円前後
- 訴訟提起 10万円~30万円前後 ※場合によっては高額になることもあります
(3)報酬金
報酬金とは、会社から得た経済的利益に対してかかる費用です。経済的利益の額に応じて変わってきます。報酬金の相場は以下のとおりです。
- 獲得した経済的利益の額に対する 16%~30%前後
※着手金が高額となる場合などには、報酬割合が比較的低くなる傾向です
6.よくある質問
以下では、セクハラ被害についてよくある質問を3つ挙げました。この3つについて回答していきます。
6-1.セクハラとパワハラの違い
よくある質問の一つ目は、「セクハラとパワハラの違いは何ですか?」です。セクハラもパワハラもハラスメントの一種であることは共通しています。ハラスメントとは、人に対する嫌がらせやいじめなどの迷惑行為を指します。
セクハラの場合、その嫌がらせやいじめが性的なことに起因するのに対し、パワハラは暴言や暴力に起因します。迷惑行為である点は共通しますが、迷惑行為が性的なことか、または暴言や暴力かによってセクハラかパワハラかに分けられます。
6-2.セクハラ被害を訴えた場合の解雇リスク
よくある質問の二つ目は、「セクハラ被害を訴えた場合、解雇される可能性はありますか?」です。
結論から申し上げますと、セクハラ被害を訴えたこと自体は解雇事由に当たりません。解雇の要件は厳格に定められており、少なくとも客観的に合理的理由があり、社会通念上の相当性があることが必要です。セクハラ被害を訴えることは被害者として正当なものであり、それ自体が解雇事由に当たることはありません。
しかしながら、セクハラ被害を訴えた場合、会社との関係が悪化する場合があります。会社に居づらくなり、退職を余儀なくされることもありますし、会社から退職勧奨をされる可能性も否定できません。
ただし、原則的にはセクハラ被害を訴えることによって不利益を課せられることはあってはならないことです。そのため、不当な労働環境の悪化や退職勧奨については、早めに弁護士に相談してみましょう。
6-3.セクハラ被害を会社に報告する際の注意点
よくある質問の三つ目は、「セクハラ被害を受けたことを会社に報告する際の注意点は何ですか?」です。
セクハラ被害を受けた場合、まず上司や人事部に相談することが多いでしょう。会社に報告すると、会社は事実関係について詳細にヒアリングを行います。その際、セクハラ被害を受けたと主張するだけでは、会社は取り合ってくれない可能性があります。よって、会社に報告する際には、客観的な証拠をそろえておく必要があるでしょう。
7.まとめ
セクハラ被害を受けたときの相談の流れ、労働審判の手続、弁護士への相談やメリットなどについて解説しました。セクハラ被害を受けた場合、精神的なダメージが大きいと思いますが、自分1人で悩まずに、早めに弁護士に相談してみましょう。セクハラ問題に強い弁護士であれば、強い味方となってくれるはずです。
担当者
-150x150.png)
- 法律事務所リーガルスマート弁護士
-
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
担当記事
 不当解雇2月 28, 2024突然の解雇されたらどうなる?手当や対処法を弁護士が解説!
不当解雇2月 28, 2024突然の解雇されたらどうなる?手当や対処法を弁護士が解説! 不当解雇2月 16, 2024無断欠勤は解雇になる?解雇される欠勤日数などを弁護士が解説!
不当解雇2月 16, 2024無断欠勤は解雇になる?解雇される欠勤日数などを弁護士が解説! その他2月 16, 2024確実に退職できるやむを得ない理由とは?具体例を弁護士が解説!
その他2月 16, 2024確実に退職できるやむを得ない理由とは?具体例を弁護士が解説! その他2月 5, 2024非正規雇用とは正規雇用との違いや課題点などを弁護士が解説!
その他2月 5, 2024非正規雇用とは正規雇用との違いや課題点などを弁護士が解説!