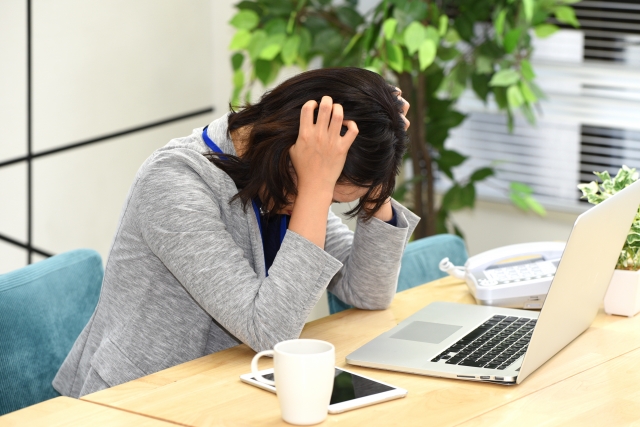ハラスメント
職場いじめのよくあるパターンは?相談先や対処法を弁護士が解説

職場の人たちが口をきいてくれない、大勢の前で叱られる、とてもこなすことができない量の業務を与えられる・・・こういった経験をされたことはないでしょうか。ご自身はご経験がなかったとしても、友人がこのような目に遭ったという話を聞いたりしたことがあるかもしれません。
こういった職場のいじめは昔から存在していましたが、近年増加傾向にあります。厚生労働省が発表した令和3年度「個別労働紛争解決制度の施行状況」では、「いじめ・嫌がらせ」が引き続き最多という結果が出ています。
今回の記事では、職場いじめのよくあるパターン、職場いじめの対象になりやすい人の特徴などを説明した上で、職場いじめに遭った場合の対処法について詳しく解説します。
職場でいじめを受けている方や、もしかしたらいじめかもしれないと悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1.職場いじめのよくあるパターン
職場いじめと一言で言っても様々なパターンがあります。以下では、典型的な職場いじめのパターンを3つご紹介します。
1-1.暴言や暴力
職場いじめのよくあるパターンの1つ目は、暴言や暴力です。パワハラの一種であり、セクハラと並んで慰謝料請求の対象となりやすいパターンです。
例えば「役立たず」や「死ね」といった人格を否定するような暴言、胸倉をつかまれたり足蹴りされたりする暴力が挙げられます。
暴言や暴力は民事的な損害賠償だけでなく、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪などの刑事事件にもなる可能性があります。
近年はコンプライアンス遵守の風潮が広まったためかあからさまな暴力などは減っているように感じますが、体育会系のノリの企業では未だに無くならないいじめのパターンです。
1-2.無視や仲間外れ
職場いじめのよくあるパターンの2つ目は、無視や仲間外れです。暴言や暴力といったあからさまなものよりも近年問題となっているパターンです。
暴言や暴力といったいじめはわかりやすいいじめであるため、加害者側も損害賠償請求をされるリスクや刑事事件になるリスクをおそれて気を付ける傾向にあります。
一方、無視や仲間外れは一見していじめと判断するのが難しく、加害者側も暴言や暴力といったいじめよりも行いやすい場合が多いのです。
また、暴言や暴力といった直接的ないじめよりもむしろ精神的なダメージが大きく、いじめを受けた本人は精神的な病になってしまう場合があります。
1-3.処理しきれない業務量の割り当て
職場いじめのよくあるパターンの3つ目は、達成できないようなノルマを設定し、ノルマを達成するまで家に帰ることができない等、処理しきれない業務量を割り当てるパターンです。終業時刻直前に「これやっといて」と仕事を押し付けるパターンなどもあります。
業務量が多いことは通常でもあり得るため、一見するといじめとはわからないようにも思われますが、明らかに度を越えた業務量の割り当てはいじめと判断される可能性が高いと思われます。
1-4.仕事を与えられない
処理しきれない業務量を割り当てることはいじめに該当しますが、逆に、仕事を全く与えないこともいじめに該当します。
仕事を全く与えられない場合、職場で何もすることがなくただ机に座っているだけだったり工場の隅で立っているだけだったりして終業時間まで時間をつぶさなければなりません。
何もすることがないのに毎日出勤するのは非常に苦痛であり、精神的なダメージが大きいいじめの一つです。
会社は簡単に労働者を解雇することができないため、仕事を与えないことによって自ら退職に追い込もうとする場合もあります。
2.職場いじめの対象になりやすい人の特徴
職場いじめの対象になりやすい人の特徴を4つ挙げて解説します。職場いじめに遭わないために、ご自身がいじめに遭いやすい特徴なのかどうか、チェックしてみてください。
2-1.仕事上のミスが多い
仕事上のミスが多いと、一緒に仕事をしている同僚や上司から避けられる傾向にあります。仕事のミスが多い人と仕事をすると仕事が進まず、一緒に働きたくないと思われてしまうからです。
仕事上のミスは誰にでもあるため、それだけで職場いじめになることは少ないですが、同じようなミスを何度も繰り返したり他人のアドバイスを聞かなかったりすると同僚や上司からいじめを受ける可能性が高まってきます。
2-2.遅刻や欠勤が多い
仕事上のミスが多いこととも関連しますが、遅刻や欠勤が多い人は上司や同僚から避けられがちです。
遅刻が多いと仕事の取引先に迷惑をかけたり、打合せが進まなかったりして他の人の業務が滞る可能性があるからです。
遅刻や欠勤は誰にでも起こり得るものですが、遅刻や欠席が目立たないように気をつけましょう。
2-3.反抗的な態度
上司に反抗的な態度を取ったりすると、上司に「生意気だ」と思われていじめられる原因になったりします。上司と意見が合わない場面は誰にでもあると思いますが、不用意に反抗的な態度を取るようなことは避け、建設的な意見を言うようにしましょう。
2-4.成績優秀
営業成績が良かったり、高度な作業が行えるなど、周りよりも仕事ができる場合、同僚や上司から妬まれる場合があります。仕事を頑張っているのにいじめられてはたまったものではありませんが、周りに対して成績を自慢したり、周りを下に見たりすることは慎みましょう。
3.職場いじめが起きやすい職場環境の特徴
職場いじめの対象になりやすい人の特徴について解説しましたが、そういった特徴を持っているからといって必ずしも職場いじめの対象になるわけではありません。
職場いじめが起きやすい職場環境かどうかが一つの大きな要因といえるでしょう。以下では、職場いじめが起きやすい職場環境の特徴を解説します。
3-1.残業が多い・休日が少ない
残業が多く休日が少ない職場では、従業員は疲弊し心に余裕がなくなっています。そういった職場環境では、他人のミスを許すことができず、いじめに発展するケースが多くなります。
3-2.パワハラが横行している
パワハラが横行しているような職場では、必然的にパワハラによるいじめが増えます。気に入らない部下や同僚などに対し大勢の前で叱ったりすることで、いじめの標的にされる可能性が高くなります。
3-3.人事異動が少ない
人事異動が少ない職場では、長年職場にいる従業員が職場を仕切っている環境になってしまっている場合があります。いわゆるお局様です。
お局様に嫌われてしまうといじめの対象になってしまう可能性が高いです。
4.職場いじめに関する裁判例
職場いじめついては、多くの裁判例が存在しますが、以下では代表的なものを2つご紹介します。
4-1.店長の発言がパワハラに当たるとされた事例(東京地裁平24.11.30判決)
コンビニエンスストアの店長の従業員に対する発言が従業員に精神的苦痛を与えたため、会社の事業の執行について労働者に違法に損害を加えたものと認められた事例です。結果として5万円の損害賠償が認められています。
店長は、従業員と話をしようとしていましたが、話をしているうちに従業員の退勤時間が過ぎてしまい、従業員が退勤しようとしたため、店長は従業員を制止しようとして激しい口調となりました。
具体的には、「あなた今日出勤しないでください。お金は払います。お金は払うんで来なくていいです。」「SVが本部の決定です。本部決定なんで。」と申し向け、「今日来た分と同じ給料支払われるんですか。」との従業員からの問いに対して「もちろん。最高じゃない。」と答え、その日の夜からの従業員の出勤を拒絶するとともに、「お前、ふざけんなよ。この野郎、うんじゃねえんだよおめえよ。この野郎。カメラ写ってようが何が関係ねえんだよ。こっちはよー、ばばあ、てめえ、この野郎、何考えてんだよ。」等と従業員を罵倒した上、「辞めてください。来ないでください。」「店に来んなよ。来んなよ。辞めろよ。」「どうするの。じゃ、今日来んなよ。二度と来んなよ。二度とな。」等と述べました。
店長は、以前から従業員が客とトラブルを繰り返していたことに不満を抱えており、従業員側にも問題があったようです。
しかし、従業員側に問題があるとはいえ、上記のような発言は、違法と評価されてもやむを得ないでしょう。
4-2.上司が送ったメールが侮辱的であるとされた事例(東京地判平16.12.1労判)
上司が従業員に対し「意欲がない、やる気がないなら、会社を辞めるべきだと思います」等と記載された電子メールを、従業員とその職場の同僚に送信した行為が不法行為とされ、損害賠償が認められた事例です。
上司の「やる気がないなら、会社を辞めるべきだと思います。当SCにとっても、会社にとっても損失そのものです。」という電子メールは、従業員本人のみならず同じ職場の従業員十数名にも送信されていました。
この表現は、「あなたの給料で業務職が何人雇えると思いますか。あなたの仕事なら業務職でも数倍の実績を挙げますよ。」という部分ともあいまって、従業員の名誉感情をいたずらに毀損するものであることは明らかであるとされました。
この事例は、一審では損害賠償請求が認められませんでしたが、二審では認められました。上司が送った電子メールは、従業員を叱咤督促する趣旨であり、パワーハラスメントの意図があったとまでは認められませんでしたが、精神的苦痛を与えたとされました。
5.職場いじめに遭った際の対処法
職場いじめに遭ってしまった場合、どのように対処したらよいか悩んでいる方もいらっしゃると思います。
以下では、職場いじめに遭った際の対処法について具体的に解説します。
5-1.社内窓口に相談する
例えば上司や同僚から無視されている、嫌がらせを受けているというような場合、上司や同僚に相談するわけにはいきません。その場合、人事などの社内の窓口に相談してみるとよいでしょう。上司や同僚の意見を聞いた上で、職場いじめを改善するよう動いてくれる可能性があります。
ただし、ブラック企業の場合、人事もブラックである可能性が高く、取り合ってくれない可能性があります。その場合は社外の機関に相談することを検討しましょう。
なお、昨今はコンプライアンス違反の相談に関して社内に通報窓口を設けている会社が増えてきました。通報窓口が設置されている会社は積極的に利用するとよいでしょう。通報窓口は秘密厳守で相談に乗ってくれますので、職場の上司や同僚に相談したことが漏れるリスクはありません。
5-2.社外の機関に相談する
職場いじめが横行しているようなブラック企業の場合、社内窓口は当てにならない可能性があります。逆にご自身に対する風当たりが強くなり、いじめがエスカレートする可能性もあります。そうなると、いじめが解決するどころかさらにいじめられてしまうことにもなりかねません。
職場いじめに悩んでいる場合、社外の機関に相談することを検討しましょう。社外の機関については後述しますが、いずれも職場いじめの相談に慣れていますので、相談するだけでも気持ちは楽になるはずです。
5-3.退職を検討する
社外の機関に相談しても職場いじめがなくならない場合、現在の会社を退職することを検討しましょう。退職して新たな会社に就職することで、職場いじめがない環境を手に入れることが可能になります。現在の会社で我慢するよりも、退職をしてしまったほうが好転する可能性は高まります。
会社がなかなか退職を認めてくれない方でも退職可能です。民法によれば、労働者は退職の意思表示をしてから2週間が経過することにより退職することができると定められています。退職にあたって会社の承諾を得る必要はありません。退職届を提出すればいいのです。
職場いじめがあるような会社の場合、退職を認めてくれない場合も多いと思います。その場合は退職代行サービスを利用することをおすすめします。
退職代行サービスとは、本人に代わって退職の意思を会社に伝えてくれるサービスです。会社に自ら伝えることなく会社を退職できるということで、近年利用者が急増しています。
退職代行については弁護士に相談することが可能です。弁護士であれば労働問題に関する全ての代理権を持っていますので安心です。
6.職場いじめに遭った際の相談窓口
職場いじめに遭ってしまった場合の相談窓口としては、以下の2つがあります。
6-1.総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーは、各都道府県の労働局や労働基準監督署などに設置されている相談窓口で、職場いじめをはじめ、あらゆる分野の労働相談に乗ってくれます。職場いじめの場合、必ずしも労働法令違反とはいえない場合も多いですが、そういった場合でも相談に乗ってくれます。相談料は無料で、相談者の秘密は厳守されるので安心です。
しかしながら、総合労働相談コーナーが会社と直接交渉したりはしてくれません。法的措置などを検討している場合は弁護士に依頼する必要があります。
6-2.みんなの人権110番
差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。みんなの人権110番に電話すると、かけた場所から一番近い法務局につながります。
職場いじめについても相談可能ですが、こちらも会社との直接交渉はしてくれません。
6-3.弁護士
総合労働相談コーナーやみんなの人権110番は、個人と会社との法的なトラブルを代理まではしてくれません。職場いじめについて会社との交渉を代理してもらいたい場合や、法的措置を検討している場合などは、弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士はあらゆる労働問題について依頼者を代理する権限を持っています。まずはどのような職場いじめを受けているのか弁護士に相談してみましょう。弁護士は依頼者の気持ちをヒアリングした上で、職場いじめの態様が労働法上問題があるようであれば、労働環境を改善するよう会社と交渉したり、加害者への慰謝料請求を行ったりしてくれます。
7.職場いじめについて相談する前に準備すること
以下では、職場いじめについて社内窓口や外部の機関に相談する前に準備することを3つ挙げて解説します。
7-1.職場いじめの経緯をまとめる
社内窓口や外部の機関に職場いじめの相談をするためには、その経緯をまとめておきましょう。職場いじめの経緯がまとめられていないと、適切なアドバイスができない可能性があります。よって、職場いじめの経緯を簡単にまとめておくことが必要です。
相談時間が限られていることが多いため、あらかじめ以下の点を中心にまとめておきましょう。
- 職場いじめが始まった時期、頻度
- 職場いじめの加害者、態様
- 職場いじめについて社内窓口に相談したときの時期、内容
- 職場いじめにより通院をしたことがある場合はその時期、診断結果
7-2.職場いじめの証拠を収集する
職場いじめがあったことを社内窓口や外部の機関に相談しても、証拠がなければ事実かどうかを確認することができず、会社に職場いじめを認めてもらえない可能性があります。労働審判や裁判になった場合には、職場いじめが行われたことの証拠を提出する必要があります。よって、職場いじめがあったらなるべく詳細に証拠を収集しておく必要があります。
具体的にどのように証拠を収集するかは弁護士に相談すべきですが、例えば以下のような証拠を収集しておくのが望ましいでしょう。
- 職場いじめがあったときの加害者の発言を録音又は録画したもの
- 職場いじめをされたときの加害者からのメールやLINEなどのメッセージ
- 職場いじめについて人事等の社内窓口に相談したときのメール
- 職場いじめを受けたことを記録したメモや日記
- 職場いじめを理由に通院をしたことがある場合はその日付と診断書
8.職場いじめや退職について弁護士に相談するメリット
職場いじめや退職については様々な機関に相談することが可能ですが、その中でも弁護士に相談を行うメリットは大きく分けて3つあります。
8-1.証拠収集についてのアドバイスがもらえる
弁護士に相談するメリットの一つ目は、弁護士のアドバイスによりご自身で収集するよりも多くの証拠が収集可能である点です。職場いじめに対して会社と交渉したり、加害者に対し法的措置を取るためには、職場いじめがあったことを立証する証拠の存在が重要になってきます。
弁護士に相談すれば、トラブルの当初から適切な証拠を収集することが可能です。法律の専門家である弁護士は、裁判や審判で有利になり得るかを考慮しつつ、証拠収集について依頼者に適切なアドバイスをします。よって、依頼者自らが証拠を収集するよりも適切な証拠を多く収集できる可能性が高まるというメリットがあります。
8-2.職場いじめについての過去の事例を調査してくれる
弁護士に相談するメリットの三つ目は、職場いじめについての過去の裁判例などを調査・検討してくれるので、ご自身が受けている職場いじめに対する慰謝料請求などが法的に認められるのかが客観的にわかる点です。
労働問題に精通した弁護士に依頼すれば、過去の裁判例や労働審判を調査して的確なアドバイスをしてくれます。また、職場いじめの加害者に慰謝料請求などが可能と判断すれば、交渉や法的措置を取り、過去の事例をもとに有利な主張を組み叩てくれます。よって、自分で交渉や法的措置を行うよりも有利となることは間違いないでしょう。
8-3.全ての労働問題を代理してくれる
弁護士に相談するメリットの二つ目は、自ら会社や加害者と交渉したり、裁判に出頭したりする必要がなくなる点です。弁護士はあらゆる労働問題について本人を代理する権限を有しています。弁護士に依頼して交渉を行えば、ご自身が直接交渉する必要はなく、精神的な負担から解放されます。職場いじめを受けている被害者にとって、会社や加害者を相手に交渉や慰謝料請求を行うことは多大な心痛を伴うことから、弁護士が代理してくれるのは心強いでしょう。
9.まとめ
今回の記事では、職場いじめのよくあるパターンや職場いじめが起きやすい職場環境について説明した上で、職場いじめに遭ってしまった際の対処法について詳しく解説しました。
職場いじめに遭ってしまった際には、社内窓口への相談、社外の機関への相談、退職という3つの対処法があることを説明しました。このうち、社外の機関への相談は職場いじめに対する悩みについて具体的なアドバイスをしてくれますのでおすすめです。また、職場いじめが起こりやすい職場環境で働き続けるのは多大なストレスを伴うため、退職を検討すべきであることをお伝えしました。退職代行サービスの利用もおすすめです。
弁護士は職場いじめに関する労働問題に熟知していますし、あらゆる労働問題についてご本人を代理することが可能です。
職場いじめが起きやすい職場環境に耐えられず悩んでいる方や退職を検討している方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
担当者
-150x150.png)
- 法律事務所リーガルスマート弁護士
-
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
担当記事
 不当解雇2月 28, 2024突然の解雇されたらどうなる?手当や対処法を弁護士が解説!
不当解雇2月 28, 2024突然の解雇されたらどうなる?手当や対処法を弁護士が解説! 不当解雇2月 16, 2024無断欠勤は解雇になる?解雇される欠勤日数などを弁護士が解説!
不当解雇2月 16, 2024無断欠勤は解雇になる?解雇される欠勤日数などを弁護士が解説! その他2月 16, 2024確実に退職できるやむを得ない理由とは?具体例を弁護士が解説!
その他2月 16, 2024確実に退職できるやむを得ない理由とは?具体例を弁護士が解説! その他2月 5, 2024非正規雇用とは正規雇用との違いや課題点などを弁護士が解説!
その他2月 5, 2024非正規雇用とは正規雇用との違いや課題点などを弁護士が解説!