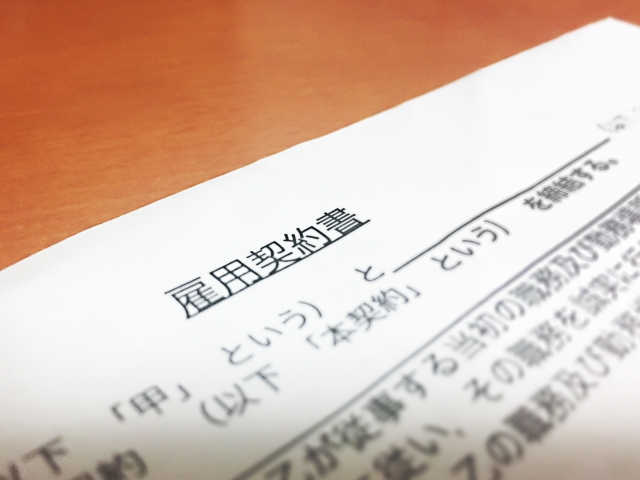その他
雇用契約とは?契約を結ぶ際のポイントやトラブルの対処法を解説
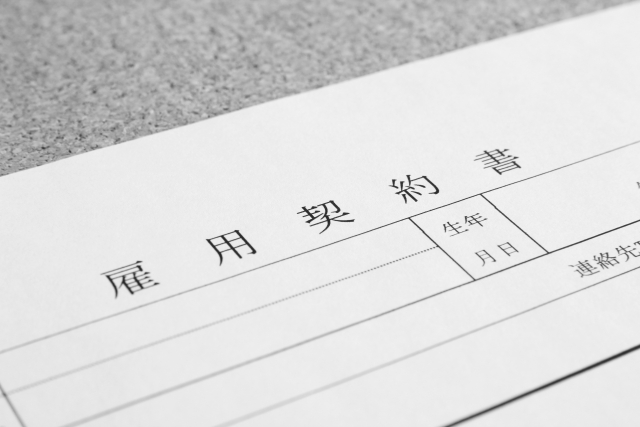
1.はじめに
雇用形態に関係なく、仕事の採用が決まれば雇用契約を使用者と結ぶことが一般的です。
雇用契約書と呼ばれる書面に署名・捺印を行い、労働者と使用者の雇用契約が成立します。
この雇用契約時には、労働条件をしっかりと確認することが大切です。
労働条件を確認せずに雇用契約を締結すれば、あとからトラブルになってしまう恐れがあります。
また、雇用契約書のないまま仕事を開始することもトラブルを招く原因になりかねません。
そこで今回は、雇用契約を結ぶ際のポイントや、雇用契約におけるトラブルの対処法について解説します。
2.雇用契約とは
そもそも雇用契約とはどういったものなのでしょうか?
雇用契約や、雇用契約に似た労働契約、業務委託契約との違いについてご紹介します。
2-1.雇用契約と労働契約の違い
会社に雇用される際には、雇用契約や労働契約を締結します。
雇用契約とは、民法第623条で規定されている「雇用」に関する契約を指します。
民法第623条では以下のように規定されています。
「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」
引用:民法|e-Gov法令検索
つまり、雇用契約によって労働者は使用者から賃金を受け取る代わりに仕事へ従事することを約束し、使用者は労働者へ仕事をしてもらう代わりに賃金を支払うことを公的に約束することになります。
雇用契約と似たような契約に、労働契約というものがあります。
労働契約とは、労働基準法や労働契約法で規定されている「労働条件」に関する契約を指します。
労働契約法第6条では以下のように規定されています。
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」
意味合いとしては雇用契約と労働契約に大きな違いはありません。
厳密には異なる部分もありますが、実務上では同じような位置付けで取り扱われています。
2-2.雇用契約と業務委託契約の違い
会社と締結する契約の種類に「業務委託契約」というものも存在します。
業務委託契約とは、企業が他の事業主に業務の委託や請負を依頼する際に締結する契約を指します。
一方が注文を受けた業務の遂行を約束し、もう一方がその業務の成果に対して報酬を支払うという契約です。
雇用契約は労働者と使用者という関係間で締結される契約になるため、労働基準法や労働契約法などの法律によって保護されています。
一方で、業務委託契約は企業と企業や法人などの事業主間で締結される契約です。
そのため、雇用契約のように労働者として労働法上の保護を受けられないという違いがあります。
3.雇用契約締結時の必要手続
3-1.雇用契約時に必要な書類
労働者と使用者が雇用契約を結ぶ際には、労働条件を明示することが労働基準法第15条にて義務付けられています。
そのため、雇用契約時には「雇用契約書」と「労働条件通知書」という書類を使用者側が作成し、労働者に明示することが一般的です。
(1)雇用契約書
雇用契約書は、労働者と使用者が労働条件について合意して雇用契約を締結したことを示す書類です。
雇用契約書には終業時間や業務内容などの労働条件が記載されており、当該労働者と使用者の双方が内容に同意をして署名・捺印をします。
雇用契約書の作成は法律で義務付けられていません。
使用者が労働者に対して労働条件を明示することは義務付けられていますが、労働条件通知書で労働条件を明示していれば雇用契約書がなくても法律に違反していないことになります。
しかし、労働者と使用者間でのトラブルを回避するために、双方が合意していることを証明するために雇用契約書を取り交わすことが一般的です。
(2)労働条件通知書
労働条件通知書は、労働基準法第15条に定められた労働条件の明示の義務に基づいて作成される書類です。
明示する義務のある項目は、以下の通りになります。
- 労働契約の期間
- 有期労働契約の更新の基準
- 就業場所と従事すべき業務内容
- 始業及び終業の時刻
- 所定労働時間を超える労働の有無
- 休憩時間、休日、休暇
- 賃金の決定計算、支払方法、賃金の締切、支払時期
- 退職に関する事項
上記は「絶対的明示事項」になるため、労働条件通知書に必ず明記しなければならない項目です。
一方で、休職や退職手当に関する条件などは「相対的明示事項」とされ、口頭の明示だけでも問題ないとされています。
しかし、トラブルを避けるために就業規則などで明記されていることが多いです。
3-2.雇用契約締結時の対応手順
雇用契約の締結では、企業側からさまざまな手続きを求められます。
一般的に、以下のような手順で雇用契約の締結は進められます。
(1)雇用契約書・労働条件通知書の交付
雇用契約を締結するにあたって企業側は、雇用契約書と労働条件通知書を交付します。
雇用契約書は交付が義務付けられていませんが、労働条件は明記する義務があります。
そのため、必ず内容を確認するようにしましょう。
労働条件通知書や雇用契約書に問題がなければ、署名・捺印をします。
(2)必要書類の提出
入社時にはさまざまな書類が必要になります。
必要書類をあらかじめ知っておくと事前準備を行うことができ、スムーズに会社へ提出できます。
入社時に必要となる書類には、次のようなものが挙げられます。
- 署名と捺印をした雇用契約書
- マイナンバーカード
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 健康診断書
- 源泉徴収票(中途採用の場合)
(3)税金関係の手続き
入社した後は、税金関係の手続きが早急に行われます。
労働者の生活に関係するため、税金関係の手続きは非常に重要です。
雇用保険や社会保険、住民税、所得税の手続きが行われます。
こうした手続きは労働者が自ら行う必要はなく、使用者である企業側が手続きを行います。
(4)法定三帳簿の手続き
税金関係の手続きのように早急に行う必要はありませんが、入社後には社内で必要になる手続きがあります。
その手続きが、「法定三帳簿」の手続きです。
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の3種類の書類を法定三帳簿と呼び、使用者側が作成して保管することが労働基準法に定められています。(労働基準法第107条・第108条)
4.雇用契約を結んでいないとどうなる?
使用者は労働者に労働条件を明示する義務が法律で定められていますが、雇用契約書に関する法律はありません。
そのため、雇用契約書などの書面で契約をするのではなく、口約束であっても双方が合意していれば雇用契約は成立します。
しかし、雇用契約書がないまま雇用契約を結ぶことは、さまざまなトラブルが起こり得ると考えられます。
4-1.求人情報と労働条件が異なる
雇用契約書がなければ、求人情報と実際の労働条件が異なるというトラブルが起こる可能性があります。
求人情報の内容は、あくまでも一般的な求人情報であり、具体的な従業員との労働条件は個別に労働者と合意しなければなりません。
そのため、求人情報に記載されている労働条件が、そのままどの応募者にも適用されるとは限りません。
そして、最初から労働者を騙すつもりで好条件の求人を乗せて求人者を募り、実際には劣悪な条件で働かせたというケースでなければ違法にはならないと考えられます。
しかし、雇用契約書に求人情報と同じ労働条件が記載されていたのであれば、求人情報と実際の労働条件が異なる場合は会社と交渉や弁護士に相談することができます。
4-2.契約内容が不明確になる
雇用契約書は、使用者と労働者の双方が労働条件に合意して雇用契約をしたという証拠になる書面です。
口約束では合意したことを証拠として残すことができず、後で「言った・言わない」の争いが起こる恐れがあります。
例えば、雇用契約書がなければ使用者側と労働者側で試用期間の認識にズレが生じてしまい、試用期間の有無や待遇について「言った・言わない」といったトラブルになるかもしれません。
契約内容が不明確な状態は労働者にとって不利であり、トラブルが起こりやすくなるといえます。
4-3.雇用トラブルになった場合の証拠がない
使用者と何らかの雇用トラブルになった場合、できるだけ多くの証拠を集める必要があります。
証拠が多いほど労働者側の主張は認められやすくなります。
しかし、雇用契約書がないということは、雇用に関する権利を主張するための重大な証拠が欠けていることになります。
証拠がなければ主張は認められず、労働者側が泣き寝入りすることになってしまうこともあるでしょう。
4-4.就業規則が使用者に有利になる
雇用契約だけではなく労働条件通知書もないというようなケースでは、労働者の労働条件は就業規則が指針となります。
就業規則は労働基準法に基づいた内容でなければなりませんが、雇用契約や労働条件通知書がないような会社では就業規則も違法な内容になっている可能性があります。
例えば、有給休暇は自由に取得できない、就業規則に違反した場合は即解雇、など使用者にとって有利かつ違法な内容のものがあるかもしれません。
こうした内容の就業規則は違法であり、不当に権利を侵害されている労働者側は訴訟を起こすことが可能です。
4-5.個別の雇用契約が適用されない恐れがある
雇用契約の際に就業規則よりも有利な労働条件を定めた場合、個別の雇用契約の内容が就業規則よりも優先されることが法律で定められています。(労働契約法第7条)
しかし、雇用契約書がなければ、個別に就業規則よりも有利な労働条件を定めたのかどうか証明することはできません。
そのため、使用者が個別で労働条件を定めたことを認めない限りは、就業規則に基づいた労働条件が適用されることになってしまいます。
5.雇用契約を結ぶ際のポイントと注意点
雇用契約は労働者を守るための非常に大切な契約です。
雇用に関するトラブルが起こらないようにするために、雇用契約を結ぶ際には次のポイントと注意点を押さえるようにしましょう。
5-1.雇用形態に関係なく雇用契約書を作成してもらう
雇用契約書の作成は義務付けられていないものの、労働者と使用者の間では雇用契約を結ぶことが法律で定められています。
そして、雇用契約は雇用形態に関係なく必要なものです。
そのため、一般的にはアルバイトやパートタイムでも雇用の際には雇用契約書に署名が必要なことが多いです。
アルバイトやパートで雇用契約書がないという場合は、使用者に雇用契約書を作成してもらうようにしましょう。
5-2.労働条件が明示されているか確認する
雇用の際には労働条件を明示することが法律で定められているため、雇用契約書や労働条件通知書で労働条件が明示されているのか確認しましょう。
絶対的記載事項は必ず明示されなければならない労働条件ですし、相対的記録事項も就業規則等で確認できるようにされていなければなりません。
とくに注意して確認すべき部分をご紹介します。
(1)労働契約の期間
正社員の場合は雇用期間の定めはありませんが、契約社員やアルバイト・パートタイムでは期間を定めている有期雇用契約の場合があります。
有期雇用の場合、契約期間や更新の可能性の有無、更新の条件などが明示されていなければなりません。
有期雇用の方は、必ず契約期間等の内容の明示を確認しましょう。
(2)就業場所、業務内容
雇用後に実際に働く場所や従事する業務内容は、絶対的記録事項です。
実際に働き始めると求人情報と就業場所や業務内容が異なるというトラブルを防ぐことができます。
また、雇用後に労働者の配置転換の可能性がある場合、「業務上必要があれば就業する場所または従事する業務内容の変更を命ずることがある」という内容が明記されることが多いです。
こうした内容が記載されておらず、雇用後に急な勤務地変更等が言い渡された場合、不当な命令として主張できる可能性があります。
(3)就業や休憩時間、時間外労働
始業時間・終業時間・休憩時間について明示されているか確認します。
また、時間外労働に関するトラブルは多いので、必ず確認すべきポイントだといえます。
ただし、労働条件通知書に記載が義務付けられているのは時間外労働の有無です。
みなし残業代が給与に含まれている場合などがあるので、時間外労働の扱いについて不明点がある場合は事前に確認すべきでしょう。
(4)賃金
賃金は労働者にとって非常に大切な労働条件です。
賃金の計算方法や賃金の締め切り、支払い時期などについて記載されているはずなので、必ず確認しましょう。
賞与については有無のみが記載義務になるため、支給条件の記載がない場合は確認しておくと安心です。
(5)退職や解雇に関する事項
入社前に退職や解雇について確認することは気が引けると考える方もいるかもしれませんが、退職に関するトラブルは多いので、必ず確認しておくべき事項です。
退職に関する事項では、定年制度や継続雇用制度の有無、自己都合で退職する際のルール等を確認します。
また、解雇に関する事項では、解雇事由を確認します。
解雇事由に関しては労働条件通知書には詳細が記載されておらず、就業規則に記載されているケースが多いです。
5-3.労働条件や契約内容を理解した上で雇用契約を締結する
入社前には、労働条件通知書や雇用契約書等で労働条件や契約内容を確認できることが一般的です。
そして、その労働条件や契約内容に労働社と使用者が合意して署名・捺印をすることで、双方の合意が証拠として残ることになります。
そのため、労働条件通知書や雇用契約書にしっかりと目を通し、内容を理解した上で雇用契約書に署名・捺印するようにしましょう。
契約書に署名・捺印する前に疑問点や不明点は使用者へ確認し、説明してもらうことが大切です。
6.雇用契約のトラブルを弁護士に依頼するメリット
雇用契約に関するトラブルが起こった場合、個人で解決することは簡単ではありません。
労働者側が泣き寝入りすることになるケースも多いです。
そのため、雇用契約のトラブルが起こった場合は専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
雇用契約のトラブルを弁護士に依頼するメリットには、次のようなことが挙げられます。
6-1.法的な解決策を見つけられる
雇用契約に関する問題は複雑であり、解決には知識も必要です。
そのため、トラブルがあってもどのように対処すればいいのか分からないという場合や、そもそも法的に問題があるのか判断できないという場合も多いでしょう。
弁護士に相談すれば、法的な観点から問題点を見つけてもらうことができます。
具体的な解決策についても提案してもらうことができ、依頼すれば解決に向けて対応を任せることができます。
まずは労働問題に強い弁護士へ相談し、問題点や解決策を見つけてから依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
6-2.証拠の有効性や収集方法のアドバイスを得られる
雇用契約の問題を解決するには、証拠が重要です。
証拠がなければ、「そんなことは言っていない」「身に覚えがない」と相手に反論や否定されてしまう恐れがあります。
こうした反論や否定も証拠があれば、覆すことができます。
しかし、個人で戦うには証拠の有効性や証拠の収集方法が分からず、会社と戦うことが難しい状態に陥ってしまいます。
弁護士に依頼すれば、証拠の有効性について判断してもらうことが可能です。
また、証拠がない場合でも、証拠の集め方について具体的なアドバイスを得られます。
証拠がないからといって泣き寝入りするのではなく、まずは弁護士に相談してみましょう。
6-3.会社側が対処してくれるようになる
労働問題を個人で会社に交渉することは簡単ではありません。
会社に対して問題点を訴えたとしても、聞く耳を持ってもらえないというケースは珍しくありません。
むしろ、直接交渉することで会社で居心地が悪くなり、不利な立場に追い込まれてしまうケースもあります。
弁護士が介入すれば、これまで聞く耳を持たなかった会社側も対処せざるを得ない状況になります。
なぜならば、弁護士が介入するということは法的手段を取る一歩手前の段階だからです。
会社側も訴訟等は避けたいと考えるため、真髄に対応するようになることが期待できます。
6-4.弁護士が窓口になって対応してくれる
弁護士に依頼をすれば、代理人としてあなたの窓口になってくれます。
主張を立証するための資料収集や書類の作成、会社との交渉など全てを任せられます。
こうした書類作成や交渉は、個人で行えば時間と労力を費やすことになります。
精神的な負担も大きくなり、最終的に諦めてしまうような事態になり兼ねません。
弁護士は戦略を立てた上で会社と交渉を行い、より有利な条件で問題解決を目指します。
弁護士が味方になってくれているという点も心強く、精神的な負担も軽減されるでしょう。
6-5.労働審判や訴訟にも対応できる
会社との交渉で問題が解決できない場合、労働審判や訴訟へ移行することもあります。
労働審判や訴訟では、申立手続きや法的主張を行う準備が必要です。
個人では専門的な知識がないため、申立手続きで時間を要してしまいます。
書類に不備があれば再申立が必要になりますし、申立が受理されても労働審判や訴訟で有利に主張することは難しいでしょう。
労働審判や訴訟を有利に進めるためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。
7.まとめ
労働者と使用者が雇用契約を結ぶことや、労働条件を明示することは法的に義務付けられています。
そのため、労働条件通知書や雇用契約書に労働条件が明示されており、労働者は合意の上で契約書に署名することになります。
雇用契約を結ぶことで労働者は法的に守られるため、トラブルを避けるためにも労働条件を確認した上で雇用契約を締結するようにしましょう。
労働条件や雇用契約で疑問や不安がある場合は、労働問題に強い弁護士に相談してみてください。
早急に相談することで、トラブルを未然に防げる可能性が高まります。
担当者
-150x150.png)
- 法律事務所リーガルスマート弁護士
-
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
担当記事
 不当解雇2月 28, 2024突然の解雇されたらどうなる?手当や対処法を弁護士が解説!
不当解雇2月 28, 2024突然の解雇されたらどうなる?手当や対処法を弁護士が解説! 不当解雇2月 16, 2024無断欠勤は解雇になる?解雇される欠勤日数などを弁護士が解説!
不当解雇2月 16, 2024無断欠勤は解雇になる?解雇される欠勤日数などを弁護士が解説! その他2月 16, 2024確実に退職できるやむを得ない理由とは?具体例を弁護士が解説!
その他2月 16, 2024確実に退職できるやむを得ない理由とは?具体例を弁護士が解説! その他2月 5, 2024非正規雇用とは正規雇用との違いや課題点などを弁護士が解説!
その他2月 5, 2024非正規雇用とは正規雇用との違いや課題点などを弁護士が解説!