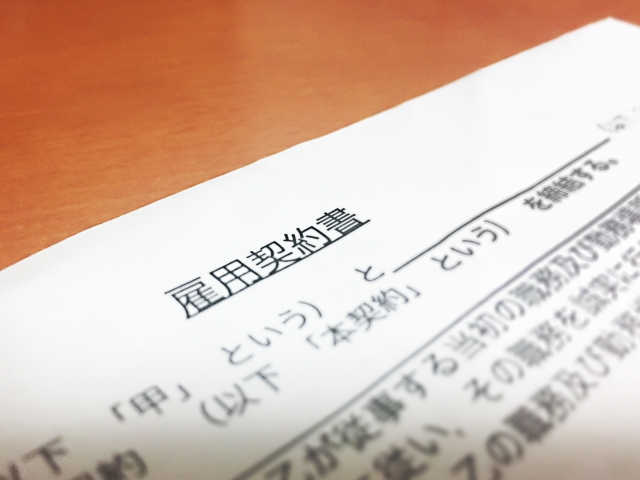その他
有給休暇を会社に拒否された!拒否された際の対処法を解説!

働いていれば誰しも、体調不良や急な用事などで休まざるを得ない状況が出てくるものです。そんな時、利用を検討したいのが有給休暇です。
ところが、「有給休暇を申請したら忙しいと拒否された」「休むには詳細な理由が必要だと言われた」などのように有給休暇が取得できず、対処方法を探している方も多くいらっしゃいます。
そもそも会社は有給休暇を拒否できるのでしょうか。また、拒否された場合はどのような行動を取れば良いのでしょうか。
本記事では有給休暇の取得条件や会社が拒否することの違法性、拒否された場合の対処法などについて解説します。有給休暇のトラブルで悩んでいる方はぜひ最後までお読みください。
目次
1.有給休暇とは
1-1.有給休暇とは何か
有給休暇とは、平たく言えば、賃金が支払われる休暇のことを指します。通常、会社を休むと賃金は減額されますが、有給休暇を使用したお休みについては賃金の支払いが義務付けられています。
有給休暇は一定の条件を満たした労働者全員に対し、所定休日とは別に与えられます。所定休日は会社が定めた休日のことです。例えば、会社で土日が休みだと定められている場合、有給休暇は土日以外の平日に取得することができます。
フルタイムの正社員や契約社員はもちろん、アルバイトやパートで働く労働者であっても、要件に該当すれば、有給休暇を取得することができます。
1-2.有給休暇の義務化
2019年4月から、会社が労働者に対して年5日の有給休暇を取得させることが義務化されました。
対象は有給休暇が年10日以上付与される労働者全員です。正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態は問われません。
就業規則に取得時季を指定する旨が定められている会社では、年5日の有給休暇の時季指定ができます。ただし、労働者の意見を聴取した上で、できる限り意見を尊重して決めなければなりません。労働者は定められた期間内に有給休暇を取得することが求められます。
義務化が導入された理由としては、日本の有給休暇消化率が世界各国と比較して非常に低いことが挙げられます。働き方改革を後押しし、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的としています。
なお、この年5日の有給休暇を取得させなかった場合、会社側には30万円以下の罰金が課される可能性があります。1人あたり30万円以下の罰金となるため、該当の労働者が複数人いる場合は多大な費用を支払う必要が出てきます。罰則を避けるためにも、会社は労働者の有給休暇取得状況について常に把握しておくことが重要です。
2.有給休暇を取得できる条件
2-1.有給休暇取得の2つの条件
有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社の義務であることが労働基準法で定められています。とはいえ、制限なく誰でもいくらでも取得できる訳ではありません。
労働基準法39条によると、有給休暇を取得するための条件は以下の2つです。
- 6ヶ月以上継続的に勤務している
- 全労働日の8割以上出勤している
それぞれ詳しく見ていきましょう。
(1)6ヶ月以上継続的に勤務している
会社に6ヶ月以上在籍していれば、6ヶ月以上の継続勤務の条件を満たすことになります。会社に出勤を続ける必要はありません。
例えば4月1日付で入社した場合、10月1日から「6ヶ月以上の継続勤務」に該当するようになります。
パートやアルバイトであっても条件は同じです。また、定年退職後に再雇用した場合、実質的に雇用関係が継続していると認められれば継続勤務として扱われます。
(2)全労働日の8割以上出勤している
全労働日の8割以上出勤しているかについては「出勤日数÷全労働日の日数」で計算します。
- 全労働日の日数・・・会社が定めた休日を除いた日数
- 出勤日数・・・全労働日のうち、出勤した日数
以上の計算結果が0.8以上となれば、条件を満たすことになります。
パート・アルバイトの労働者であれば「出勤日数÷所定労働日数」で計算します。例えば週5日勤務で雇用した労働者が、平均して週4日出勤した場合、出勤率は80%です。この場合、6ヶ月の勤続期間を経て有給休暇を取得できます。
なお、出勤率の計算に当たっては注意事項があります。
まず、全労働日と出勤日には、以下の日・期間が含まれます。
- 業務が原因とされる傷病による休業
- 産前産後休暇
- 育児休業および介護休業
また、全労働日と出勤日から除外される日として、以下が挙げられます。
- 使用者の責任による休業日
- 休日出勤した日
- 休職期間
その他、生理休暇や慶弔休暇など、取り扱いを会社の就業規則で定めることができる日もあります。条件に該当するかどうかは人事部などに問い合わせてみると良いでしょう。
2-2.付与日数の計算方法
前述した2つの取得条件を満たす労働者は有給付与の対象です。有給休暇の付与日数は労働基準法によって定められた10日が基本となり、これに加え、勤続年数によって有給休暇が増えていきます。
有給休暇の付与日数はフルタイムの一般労働者とパート・アルバイトの労働者で異なります。ただし、パート・アルバイト労働者であっても、所定労働時間が30時間以上かつ週5日以上の勤務契約をしている場合はフルタイム労働者と同様に考えます。
(1)一般労働者(フルタイム)の場合
フルタイムの労働者および所定労働時間が30時間以上かつ週5日以上の労働者については、以下の表に従って付与日数が決まります。
| 勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
入社日から6ヶ月後を最初の付与日とし、以降1年ごとに付与日数が1〜2日ずつ増えていきます。最大で20日まで付与され、6年5年以上勤務しても付与日数は増えません。
(2)パート・アルバイトの場合
所定労働時間が30時間未満かつ週4日以下のパート・アルバイトの労働者については、勤続年数と週の労働日数に応じて有給休暇が付与されます。これを比例付与といいます。
付与日数は以下の表のとおりです。
| 週所定 労働日数 | 年間の所定 労働日数 | 勤続 0.5年 | 勤続 1.5年 | 勤続 2.5年 | 勤続 3.5年 | 勤続 4.5年 | 勤続 5.5年 | 勤続 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
2-3.有給休暇の付与のタイミング
有給休暇の付与は基本的に入社から6ヶ月経った日に行われます。ただし、会社によっては入社日に一斉付与することもあります。
また、法定の有給休暇日数は最低限の義務規定のため、会社の判断によってそれ以上の有給休暇を与えることもできます。
2-4.有給休暇の時効
有給休暇はいつまでも取得できるものではなく、その他の請求権と同様に時効があります。労働基準法115条によると、有給休暇の時効は2年と定められています。そのため、有給休暇を消化しないで残しておいたとしても、2年で期限切れになって消えてしまいます。
一方で、見方を変えると、2年は有給休暇を保持できるということにもなります。例えば、前年度に有給休暇を5日しか使わなかったとすれば、今年度使用できる有給休暇は35日(年20日付与された場合)になります。ただし、繰越可能な有給休暇の日数は最大20日です。
3.会社は有給休暇を拒否できるのか
3-1.正当な理由なく拒否すると違法
有給休暇の取得は労働者の権利です。労働者は希望する日に有給休暇を取得することができます。労働者から有給休暇の申請があった場合、原則として会社は拒否できません。
有給休暇を正当な理由なく拒否した場合、使用者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を課される可能性があります。
3-2.会社が有給休暇を拒否できる場合
一方で、会社が有給休暇を拒否できるケースもあります。
有給休暇は労働者の権利ですが、労働者が有給休暇の申請をした日に必ず取得させなければならないとすると、会社にとって大きな不利益を生ずる恐れがあります。これを避けるために、一定の場合のみ有給休暇の取得の変更を求めることができる制度を設けています。
このように、会社が有給休暇の取得時期を変更できる権利を「時季変更権」といいます。
とはいえ、会社が時季変更権を濫用して何度も申請を拒否するなど、いつまで経っても労働者が有給休暇を取得できない状況になると困ります。これを避けるため、会社が時季変更権を使用できるのは「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」と決まっています(労働基準法39条5項但書)。
この「事案の正常な運営を妨げる場合」は個別具体的かつ客観的に判断されなければなりません。単に「業務が忙しい」「繁忙期だから」という理由での時季変更権の行使は認められません。労働者の代替要員を確保することができるのであれば、会社は代替要員を用意しなければなりません。つまり、当該労働者にしかできない職務があるなど、客観的に見て、代替要因を確保することが困難である場合にのみ、時季変更権が使用できるといえます。
加えて、有給休暇の取得が正常な運営を妨げる状況が解消されたときは、速やかに休暇を与えなければなりません。時季変更権を行使する場合には、会社と労働者がよく話し合い、なるべく双方が納得する形で有給休暇の時期を決めることが望ましいです。
3-3.退職時の有給休暇取得
退職することが決まっている場合、残っている有給休暇を消化したいと考えるのは当然です。通常時と同様に、会社は基本的に有給休暇の取得申請を拒否できません。
注意が必要なのは時季変更権についてです。会社が時季変更権を使用すること自体は可能ですが、有給休暇の取得日を退職日より後に設定することができません。退職日以降に設定してしまうと、実質的に有給休暇を拒否してしまうことになるからです。そのため、退職日間際に有給休暇を申請すると、会社側が変更を指示できなくなり、重大な損害が発生することもあり得ます。このように、会社との衝突を避けるためにも、なるべく早めにスケジュール調整をするべきです。
しかし、引き継ぎなどで退職日直前まで有給休暇を取得することができないこともあるでしょう。この場合も会社との話し合いの場を設けることをおすすめします。労働者は未消化の有給休暇の買取を求めることができるほか、退職日をずらして有給休暇を取得できるようにするなどの調整ができることがあります。
4.有給休暇を申請する際、正当は理由は必要?
4-1.有給休暇の取得に正当な理由は必要ない
会社は有給休暇の利用目的によって取得を制限することはできません。労働者は理由を申告する義務はなく、理由を確認されても「私用のため」という以上に説明する必要はありません。
なお、労働基準法上では虚偽の理由で有給休暇を申請したとしても処罰の対象になりません。しかし、就業規則に「虚偽の申告を禁止する」等の記載がある場合は、処分の対象となる可能性がありますので注意しましょう。
4-2.有給休暇の取得理由を聞くことは違法か
労働者が有給休暇の理由を申告する義務はないものの、会社が取得理由を聞くこと自体は違法ではありません。会社によっては有給休暇の申請時に取得理由を記入する欄がある場合もありますが、こちらも法律上は許されます。
ただし、労働者が理由を答えたくないという意思を示しているにも関わらず、しつこく問いただしてしまうとパワーハラスメント(いわゆるパワハラ)などに該当する可能性があります。パワハラは人格権侵害の不法行為ですから、会社に対し、民法上の損害賠償を請求することができる可能性があります。
また、取得理由がないからと言って有給休暇の取得を妨げてしまうと違法になります。労働基準法では、有給休暇を取得する際に理由を示すことを要件としていません。そのため、「理由を告げなければ有給休暇を取得できない」などのルールを設けてしまうと、労働基準法に違反することになります。
5.会社に有給休暇を拒否されたときの対処法
5-1.まずは上司と話し合う
会社に有給休暇を拒否された場合、社外への相談や法的措置を検討する前に、まずは会社側の理由を確認することが重要です。基本的に有給休暇の申請は上司に対して行いますので、上司と話し合う場を設けてみてください。
先述したように、会社には時季変更権があります。業務を他の労働者に任せることができず、やむなく有給休暇を拒否している場合も考えられます。会社側の理由をしっかり確認し、可能であれば録音や書面などの証拠を残すようにしましょう。この証拠は今後、社外に相談する際に必要になる場合がありますので、きちんと手元に置いておくことをおすすめします。
拒否理由を確認した上で、「いつであれば有給休暇を取得できるか」を話し合いましょう。時季変更権は有給休暇の時季をずらす権利であり、請求自体は拒否できません。代替案を提示するなどして交渉し、希望日の近くで取得できるように調整すると良いでしょう。
5-2.社内で解決する
上司に相談しても取り合ってくれず、いつまで経っても有給休暇を取得できない場合もあるかもしれません。繰り返し有給休暇を拒否したり、有給休暇の取り下げを強要したりすると、パワハラに当たることもあります。上司の判断で有給休暇を拒否しているのであれば、社内の人事部や労働組合に相談することも一つの方法です。
パワハラの相談があった場合、会社には再発防止策を講じる努力義務があります。人事部に相談すれば、上司への指導や配置替えなどの対処をしてくれる場合がありますので、積極的に活用してみてください。
また、労働組合も会社に対して大きな発言権を持っています。労働者が団結して作る組織ですので、労働者の相談に耳を傾け、味方になってくれる可能性があります。
5-3.労働問題の専門窓口に相談する
社内に相談窓口がない、相談すると不利益な扱いを受けるおそれがあるなど、社内では解決できない場合、労働問題を専門として扱う相談窓口に助けを求める手もあります。社外の相談窓口としては主に以下の3つが挙げられます。
- 労働基準監督署
- 法テラス
- 法律(弁護士)事務所
(1)労働基準監督署
有給休暇の取得は労働基準法で定められているので、労働基準監督署(労基)に相談することができます。直接、窓口に赴くほか、電話やメールなど匿名の相談窓口も設けられており、誰でも無料で利用可能です。
労働基準監督署の窓口でできるのは「相談」と「通報」の2つです。
「相談」では労働者に対し、法律や判例などを踏まえて、解決に向けたアドバイスを行ってくれます。希望があれば、専門家の立ち会いの上、会社側と話し合いを行う場を設けることも可能です。
「通報」では労働基準法に違反している会社を取り締まってくれます。労働者からの通報を受けた労働基準監督署は、通報内容によって会社への立入検査などを実施。検査の結果を受けて、是正勧告などの行政指導をしてくれます。行政指導には法的強制力がありませんが、従わない場合に罰則を課されるリスクがあるため、トラブルが解決する可能性は高いです。
ただし、労働基準監督署が動くことができるのは、労働基準法に違反している場合に限られます。そのため、相談・通報する上で必要なのは証拠集めです。雇用契約書や勤怠管理表、有給休暇の申請書、取得拒否されたメールや音声などを記録に残すようにしておきましょう。
また、相談・通報によって「会社にバレて立場が悪くならないか」も心配なところです。労働基準監督署には守秘義務がありますので、会社に情報提供者を伝えることを希望しない場合に勝手に明かすことはありません。
注意が必要なのは、労働基準監督署はあくまで会社の違法行為を取り締まる機関であり、会社と労働者の個人的なトラブルには介入できません。会社との交渉自体を専門家に任せたい場合は法テラスや弁護士への相談を検討しましょう。
(2)法テラス
法テラスは正式には「日本司法支援センター」といい、トラブル解決に役立つ情報を無料で提供する公的機関です。問題解決のための法制度の紹介のほか、弁護士会など適切な相談機関の紹介を行っています。
経済的に困窮しているなど一定の要件を満たせば、無料法律相談や弁護士費用の立替を行ってくれる場合もあります。費用面で相談を諦めている方もぜひ検討してみてください。全国各地に事務所を設けており、弁護士に相談する前段階として活用できます。
(3)法律(弁護士)事務所
有給休暇のような労働問題は、会社との話し合いが難航し、時に訴訟に発展することもあります。労働問題に詳しい弁護士に相談することで、有給休暇のトラブルが違法かどうかの判断や有効な証拠集めの方法を示してくれます。あらかじめ証拠を用意していれば、会社との交渉や訴訟を有利に進めることができます。
6.有給休暇に関するトラブルを弁護士に依頼するメリット
6-1.早期解決が望める
有給休暇のトラブルが発生した場合、今後の生活のためにも迅速に対応することが大切です。法律の専門家である弁護士に相談すれば、その時に必要な対応をスピーディーに行ってくれます。このため、自分で全ての手続きを行うよりも、問題の早期解決が可能です。
6-2.依頼者の代わりに交渉してくれる
働いている会社と交渉する際に強い姿勢を保つのは何かと難しいものです。感情的になってしまい、話し合いが難航するということもあり得ます。弁護士は依頼者に代わって交渉してくれるので、安心感を持って解決に向かうことができます。訴訟に発展しないように交渉することにも長けています。
6-3.訴訟に発展した場合も対応できる
時に会社との交渉が上手くいかず、訴訟に発展することもあります。弁護士は裁判を見据えて会社と話をするため、交渉から訴訟まで一貫した立場で主張することが可能です。訴訟の際の煩雑な手続きも弁護士に任せることができるので、労働者の精神的な負担が少なくて済みます。
7.まとめ
有給休暇の取得拒否のような労働問題を解決するには法的な知識が不可欠です。法律の専門家である弁護士に依頼することで、会社との交渉から訴訟まで有利に進めることができます。
弁護士はトラブル解決のプロです。有給休暇の問題を抱える労働者にとって、最適な解決策を提示してくれます。また、煩雑な手続きや会社との交渉を全て弁護士が代行してくれるため、精神的なストレスから開放されます。交渉が合意に至らず、訴訟に発展した場合にも、安心して対応を任せることができます。
有給休暇の問題で悩んだときは、一人で解決しようとせず、なるべく早く弁護士に相談してみることをおすすめします。
私たち法律事務所リーガルスマートは、有給休暇に関するトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
担当者
-150x150.png)
- 法律事務所リーガルスマート弁護士
-
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
担当記事
 不当解雇2月 28, 2024突然の解雇されたらどうなる?手当や対処法を弁護士が解説!
不当解雇2月 28, 2024突然の解雇されたらどうなる?手当や対処法を弁護士が解説! 不当解雇2月 16, 2024無断欠勤は解雇になる?解雇される欠勤日数などを弁護士が解説!
不当解雇2月 16, 2024無断欠勤は解雇になる?解雇される欠勤日数などを弁護士が解説! その他2月 16, 2024確実に退職できるやむを得ない理由とは?具体例を弁護士が解説!
その他2月 16, 2024確実に退職できるやむを得ない理由とは?具体例を弁護士が解説! その他2月 5, 2024非正規雇用とは正規雇用との違いや課題点などを弁護士が解説!
その他2月 5, 2024非正規雇用とは正規雇用との違いや課題点などを弁護士が解説!