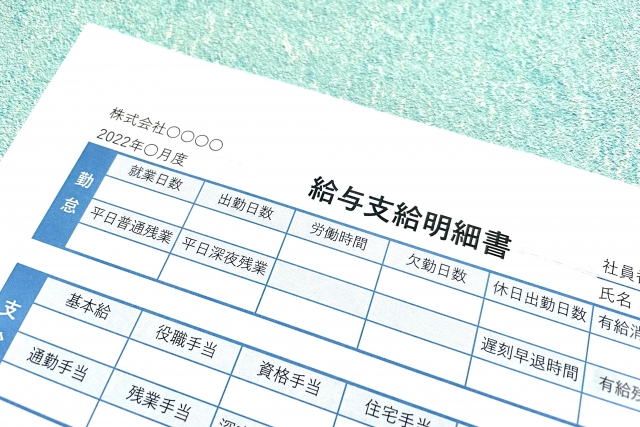残業代請求
労働基準法が定める休憩時間の定義とは?三原則を弁護士が解説!

1.はじめに
労働基準法は、会社に対して労働者に休憩を取らせる義務を定めています。
休憩時間は、労働者の心身をリフレッシュし、また会社内のコミュニケーションを図る意味でも重要です。
それでは、労働基準法は休憩について具体的にどのようなルールを定めているのでしょうか。
今回は、休憩に関する3つの区分と3つの原則を紹介します。
2.休憩に関する3つの区分とは?
⑴法律
労働基準法34条1項は、次のように定めています。
- 1項「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
⑵解説
まず注意すべきなのは、「6時間を超える場合においては」と規定している点です。
すなわち、労働基準法は、勤務時間が6時間を超えない場合には、労働者に対して休憩時間を与えなくてもよいことになります。
次に、勤務時間が6時間以上、8時間未満の場合には、休憩時間は45分でよく、勤務時間が8時間を超える場合に1時間の休憩を与えなければならないと規定しています。
まとめると、以下のようになります。
- 勤務時間が6時間未満の場合 休憩時間は与えなくてもよい
- 勤務時間が6時間以上8時間未満の場合 45分以上
- 勤務時間が8時間の場合 1時間以上
これが、休憩に関する3つの区分ということになります。
3.休憩に関する3つの原則とは?
⑴法律
労働基準法34条2項及び3項は、次のように定めています。
- 2項「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。」
- 3項「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」
⑵解説
このように、休憩時間は勤務の「途中に」(第1項)、「一斉に」(第2項)、「自由に」(第3項)与えられなければなりません。
これが休憩に関する3つの原則ということになります。
それでは、この原則について、順に解説します。
①勤務の「途中に与えなければならない」とは?
勤務の「途中に」とは、休憩時間は必ず勤務時間の途中に設けなければならないということです。
仮に勤務時間が9時から18時と定められている場合、9時から10時の1時間であったり、17時から18時の1時間であったりという休憩時間の設定は、「労働者の心身のリフレッシュ」という休憩時間の目的に沿っていないため、許されないことになります。
さらに、この原則には例外がなく、「必ず」勤務時間の途中に与えなければなりません。
②「一斉に与えなければならない」とは?
「一斉」とは、事業場におけるパートタイマーやアルバイトなどを含む全労働者を、原則同じ時間帯で休憩時間を与えるという意味と理解されています。
したがって、原則として労働者ごとに個別に休憩時間を設定したり、労働者の好きな時間帯に取らせたりすることはできません。
もっとも、これには以下の例外が認められています。
- 労使協定で「休憩時間を一斉に与えないこと」について合意がなされている場合
- 一斉に休憩を与えることで、むしろ一般社会に不便や混乱を生じさせる以下の事業
運送、販売、理容、金融保険、映像演劇、通信、病院診療所、保育所、旅館、料理飲食、官公署
- 同一空間による一斉休憩が困難である、坑内労働者
③「自由に与えなければならない」とは?
「自由に」とは、労働者が労務から完全に開放されている状態を指します。
休憩中に携帯を持たされ、呼び出しがあった場合には応じる必要がある場合や、休憩中であっても来客があった場合には対応しなければならないような場合には、労務から「完全に」解放されているとは言えないため、休憩時間とはみなされない場合があります。
もっとも、これには以下の例外が認められています。
- 警察官、消防吏員、常勤の消防団員や乳児院、児童養護施設及び障害児入居施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
- 休憩の目的を損なわない限りにおいて、事業場の規律保持上必要な制限を加えること
- 事業所内に労働者が完全に労働から解放される休憩施設や食事を取れる施設がある場合に、外出を制限すること
- 事業の正常な運営やほかの労働者の自由利用の権利を妨げる行為
- 坑内労働者
4.管理監督者について
これまで休憩についえ3つの区分と3つの原則を紹介しましたが、管理監督者については労働基準法41条に以下の定めがあります。
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
- 一 略
- 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
- 三 略
このように、「監督若しくは管理の地位にある者」=管理監督者には、これまで解説した休憩時間のルールは適用されません。
5.まとめ
いかがでしたでしょうか。
休憩時間は例外もありますが、労働基準法が会社に対して義務づけた、労働者の権利です。
このルールに違反した休憩時間は法的に無効であり、会社に対して是正を求めたり、場合によっては労働時間に該当するものとして賃金の請求ができるケースもあります。
最後になりますが、会社の休憩時間がこのようなルールに則っていない場合には、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
担当者
-150x150.png)
- 法律事務所リーガルスマート弁護士
-
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
担当記事
 不当解雇2月 28, 2024突然の解雇されたらどうなる?手当や対処法を弁護士が解説!
不当解雇2月 28, 2024突然の解雇されたらどうなる?手当や対処法を弁護士が解説! 不当解雇2月 16, 2024無断欠勤は解雇になる?解雇される欠勤日数などを弁護士が解説!
不当解雇2月 16, 2024無断欠勤は解雇になる?解雇される欠勤日数などを弁護士が解説! その他2月 16, 2024確実に退職できるやむを得ない理由とは?具体例を弁護士が解説!
その他2月 16, 2024確実に退職できるやむを得ない理由とは?具体例を弁護士が解説! その他2月 5, 2024非正規雇用とは正規雇用との違いや課題点などを弁護士が解説!
その他2月 5, 2024非正規雇用とは正規雇用との違いや課題点などを弁護士が解説!