不当解雇
解雇予告手当とは?計算方法や支給されない場合の対処法を解説!
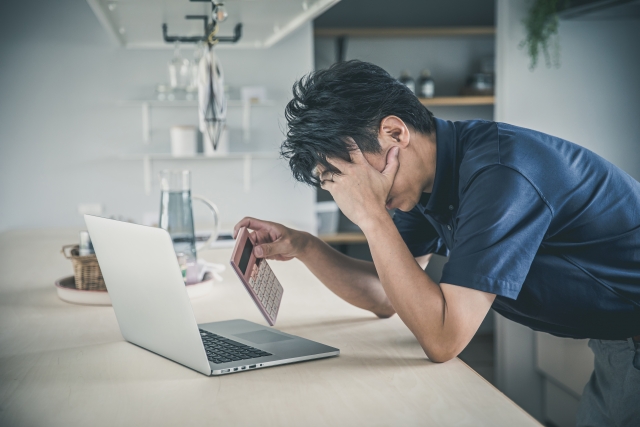
目次
1.はじめに
会社から解雇されるときには、解雇予告手当というお金をもらうことができる場合があります。
解雇予告手当という言葉自体、聞いたことがある方も少なくないのではないでしょうか。
しかし、一方で、どのような場合に、どの程度の金額が解雇予告手当として支払われるのかまでご存じの方は多くないでしょう。
今回は、解雇予告手当がどのようなものであるのか、どのような場合にいくら支払われるのかなどについて、ご説明いたします。
2.解雇予告手当とは
⑴意義
解雇は労働者の生活の基盤を喪失される重大な影響を与えるため、労働基準法20条では、少なくとも30日以上前から解雇を予告しなければならないと定められています。
ただし、会社が適切な解雇予告手当を支給したときには、解雇予告を行わずに、または法定の解雇予告期間の経過を待たずに、労働者を解雇をすることができます。
そのため、会社が、30日以上前から解雇を予告しているときには、会社は解雇予告手当を支払う必要はありません。
⑵解雇予告手当の計算方法
①計算式
解雇予告手当の金額は、次の計算式によって導き出されます。
「平均賃金1日分」×「解雇日までの期間が、30日に足りなかった日数」
②具体例
【例1】会社から「今日から解雇します(即日解雇)」と言われた場合
「平均賃金1日分」とは、「直前3カ月に支払われた賃金の総額を3カ月の総日数で割った金額」を指します。
したがって、計算式は下記のとおりとなります。
「直前3カ月に支払われた賃金総額÷3カ月の総日数」×30日
【例2】会社から「20日後に解雇します」と言われた場合
この場合の「解雇日までの期間が、30日に足りなかった日数」は、30日-20日=10日ということになります。
したがって、計算式は下記のとおりになります。
「直前3カ月に支払われた賃金総額÷3カ月の総日数」×10日
⑶解雇予告手当が不要な場合とは?
下記の場合には、たとえ30日以上前から解雇を予告していないときであっても、労働基準法21条により、例外的に解雇予告手当を支給しなくてよいとされています。
- 日雇い者(雇用期間が1ヶ月未満)が解雇される場合
- 二ヶ月以内の期間を定めて使用される者が期間内に解雇される場合
- 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者が期間内に解雇される場合
- 試用期間中の者が14日未満に解雇される場合
これらのケースは限定的なケースですので、例え雇用形態がパート・アルバイトであっても原則として会社は解雇予告手当を支給する必要があります。
3.解雇予告手当が支給されていない場合に取れる手段とは?
⑴内容証明郵便で請求する
内容証明郵便は、最も簡便で、請求した証拠が残る手段です。
解雇予告手当の支払いを請求する場合には、口頭ではなく内容証明郵便を利用することをお勧めします。
⑵労働基準監督署に相談する
解雇予告手当の不払いは労働基準法違反に当たるため、労動者は労働基準監督署へ申告できます(労働基準法104条1項)。
労働基準監督署は、会社に対して調査をおこない、違反が認めれば会社に対して行政指導や刑事処分をおこないます。 労働基準監督署から何らかの指導・処分を受ければ、会社が自発的に解雇予告手当を支払う可能性が高まります。
⑶労働審判を申立てる
労働審判は、迅速に労使紛争を解決することを目的とした法的手続きです。
令和2年のデータですが、労働審判の平均審理期間は約107日となっています。
同じく令和2年の労働関係の民事訴訟事件の平均審理期間が477日であることと比較すれば、迅速な解決が期待できる手続きであると言えます。
※最高裁「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」(第9回)
⑷訴訟を提起する
解雇予告手当を請求する最終手段として会社に対して訴訟を提起することが考えられます。
たしかに訴訟は平均審理期間が約477日と時間がかかる可能性がありますが、解雇予告手当の請求のみであれば、比較的早期の解決も見込めるのではないかと思います。
判決が確定しても会社が支払わない場合には、判決内容に従って強制執行を申し立てることが可能です。
4.まとめ
いかがでしたでしょうか。
解雇予告手当を請求することは、解雇された労働者の生活を保障するため重要な、労働者の権利です。
これを支払われずになされた解雇は労働基準法に違反している可能性が高いため、会社に対して請求することを検討しましょう。
なお、解雇予告手当を会社に請求する権利は、解雇予告日から2年間が経過すると時効消滅してしまいます(労働基準法115条後段)ので、早めに専門家に相談しましょう。
最後になりますが、解雇されたにもかかわらず解雇予告手当が支給されていない場合や、支給された解雇予告手当が上記2⑵に記載した計算方法の計算式で算出される額に満たない場合には、是非弁護士に相談されることをお勧めします。
担当者
-150x150.png)
- 法律事務所リーガルスマート弁護士
-
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
担当記事
 不当解雇2月 28, 2024突然の解雇されたらどうなる?手当や対処法を弁護士が解説!
不当解雇2月 28, 2024突然の解雇されたらどうなる?手当や対処法を弁護士が解説! 不当解雇2月 16, 2024無断欠勤は解雇になる?解雇される欠勤日数などを弁護士が解説!
不当解雇2月 16, 2024無断欠勤は解雇になる?解雇される欠勤日数などを弁護士が解説! その他2月 16, 2024確実に退職できるやむを得ない理由とは?具体例を弁護士が解説!
その他2月 16, 2024確実に退職できるやむを得ない理由とは?具体例を弁護士が解説! その他2月 5, 2024非正規雇用とは正規雇用との違いや課題点などを弁護士が解説!
その他2月 5, 2024非正規雇用とは正規雇用との違いや課題点などを弁護士が解説!








