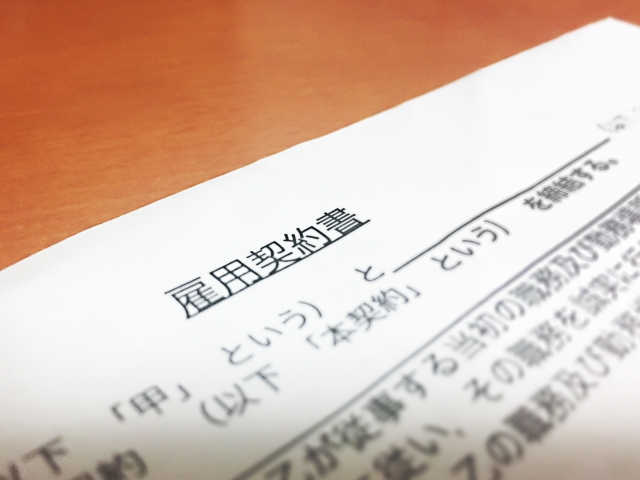その他
労働問題の相談窓口は?電話や24時間対応の無料相談窓口を紹介

毎日パワハラを受けてつらい、残業代を払ってもらえない、といったように、世の中では数多くの労働問題に関するトラブルが発生しています。
このような労働問題に関するトラブルに巻き込まれた場合に相談すべき窓口があることをご存知でしょうか。
また、相談窓口を利用する際は、24時間相談できるのか、メールやSNSでも問い合わせできるのか、費用がかかるのかなど気になることはたくさんあるでしょう。
本記事では、労働問題の相談窓口を利用する際に知っておくべきことを労働問題に強い弁護士が解説します。
具体的には、各窓口の特徴や費用、相談方法、受付時間、相談前の準備などについて解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1.労働問題について無料相談できる窓口
1-1.精神的につらい思いをしている方
(1)よりそいホットライン(24時間対応)
よりそいホットラインは、労働問題に限らず、暮らしの困りごと、DV、被災など様々な種類の悩み相談ができる窓口です。
厚生労働省の補助金事業として営まれており、電話やFAX、チャット、SNSによる相談が可能で、専門の相談員が対応してくれます。
参考:よりそいホットライン
(2)あなたのいばしょチャット相談(24時間対応)
あなたのいばしょチャット相談も、労働問題に限らず、様々な悩み相談が可能な窓口です。
チャットでの匿名相談が24時間365日できますので、電話よりも相談しやすい点に特徴があります。
これらの相談窓口は、労働問題専門の窓口ではないので、細かい相談には向いていませんが、労働問題で精神的につらい思いをしている方は頼ってみるとよいでしょう。
1-2.専門性のある行政機関に労働相談したい方
(1)総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーは、各都道府県の労働局、全国の労働基準監督署に設置されている労働問題に関する相談窓口です。
相談や助言だけでは解決しない場合は、労働問題の専門家(あっせん委員)によるあっせん制度を利用できます。
残業代未払いなどの労働基準法違反に関する案件については、労働基準監督署による調査や監督指導につながることも期待できます。
(2)労働委員会
各都道府県の労働委員会にも、労働問題の相談窓口があります。
労働委員会では、総合労働相談コーナーでは受け付けていない組合と会社との紛争の相談も受け付けています。
あっせん制度も整備されており、公益側、労働者側、使用者側の専門家三者で構成する委員会によるあっせんを受けることが可能です。
参考:東京都労働委員会
1-3.まずは気軽に悩み相談を聞いてほしい方
(1)労働条件相談ほっとライン
長時間労働、残業代未払いといった労働基準法に違反する労働条件についての相談を主に受け付けている電話相談の窓口です。
厚生労働省の委託事業であり、相談対応のほかに専門の各関係機関の紹介もしてくれます。
【受付時間】
平日:17:00〜22:00
土日祝日:9:00〜21:00
参考:労働条件相談ほっとライン
(2)ハラスメント悩み相談室
セクハラ、パワハラ、マタハラといった職場のハラスメント専門の相談窓口です。
厚生労働省の委託事業であり、電話相談、メール相談のほかSNSによる相談も受け付けています。
【受付時間】
電話相談
平日:12:00〜21:00
土日:10:00〜17:00
メール相談・SNS相談
24時間受付
参考:ハラスメント悩み相談室
(3)働く人の「こころの耳」相談
労働問題に関して生じるメンタルヘルスについての悩み相談に応じてくれる相談窓口です。
こころの健康に関する専門家が相談に応じてくれて、電話相談、LINE相談、メール相談ができます。
【受付時間】
電話相談・LINE相談
平日(月・火):17:00〜22:00
土日:10:00〜16:00
メール相談
24時間受付
参考:「こころの耳」
1-4.労働者の目線に立って解決策を考えてほしい方
(1)労働相談ホットライン
全国的な労働組合である全国労働組合総連合(全労連)が受け付けている労働相談に関する窓口です。
電話とメールで相談を受け付けています。
【受付時間】
電話相談
平日10:00〜17:00
メール相談
24時間受付
参考:労働相談ホットライン
(2)なんでも労働相談ホットライン
全労連と同様に全国的な労働組合である日本労働組合総連合(連合)が受け付けている労働相談に関する窓口です。
都道府県ごとに相談窓口があり、対面相談や電話相談の受付時間はそれぞれ異なります。
メール相談は24時間受け付けています。
これらの相談窓口は、労働組合による窓口であるため、より親身になって話を聞き、労働者と同じ目線に立って一緒に解決策を模索してくれるでしょう。
1-5.法的手段による解決を望まれる方
(1)法テラス
法テラスは、国が設置した法的トラブル解決のための総合案内所です。
労働問題に限らず、広く法律問題の相談を受け付けています。
経済的な事情によっては、無料の法律相談が受けられ、また弁護士に委任する費用の立替払いを行ってくれます。
弁護士に相談して対応を依頼したいけれど、費用が払えるか不安という方は、利用してみてはいかがでしょうか。
【受付時間】
電話相談
平日:9:00〜21:00
土:9:00〜17:00
メール相談
24時間受付
参考:法テラス
(2)法律事務所(弁護士事務所)
インターネットで「労働問題 弁護士」などと検索しますと、様々な法律事務所のホームページが出て来るでしょう。
法律事務所(弁護士事務所)というとお問い合わせのハードルが高いと感じてしまう方も多いかもしれませんが、近年では、全国対応、かつ、初回無料での相談を受け付けている法律事務所も増えてきていますし、手段についても、電話、対面、WEBなど各法律事務所によって異なりますが、自分に合った対応をしてくれる法律事務所をみつけられれば、専門的な見地からアドバイスを受けられますので、是非利用してみてください。
【受付時間・方法】
各法律事務所によって異なる。
2.労働問題でよくある相談
2-1.ハラスメントに関する相談
いわゆるパワハラ、セクハラ、マタハラといったハラスメントに関する相談は非常に多い労働相談の類型の一つです。
パワハラは、上司の部下に対する業務上の必要性及び相当性を超えた態様により生じる事例が典型例です。密室で行われるなど証拠が残らないことが多いため、録音するなど意識して証拠を残す工夫が必要でしょう。
2-2.賃金・残業代未払いに関する相談
本来払うべき賃金や残業代その他の手当が支払われないといった類型です。
労働時間の考え方や実際の残業時間の証明、固定残業代の有効性などをめぐってトラブルになるケースが多数あります。
賃金や残業代の消滅時効は3年間となっていますので、注意すべきでしょう。
2-3.人事異動に関する相談
意に沿わない転勤やグループ会社への出向を命じられるなどの事例です。
子育てに手がかかる時期や、家族の介護が必要な状況で、遠方の勤務地へ異動させられた場合に問題になります。
ワークライフバランスを重視する方が増えている昨今、トラブルに発展するケースも少なくありません。
2-4.懲戒処分に関する相談
犯罪行為や就業規則違反などを理由に、懲戒処分(懲戒解雇、降格・降職、出勤停止、減給、譴責・戒告など)を課される事例です。
そもそも違反などの事実があったかどうかや、処分が重すぎないかなどをめぐって、争いが生じやすいのです。
また、懲戒処分の手続き(弁明の機会など)が適切だったかどうかもよく問題になります。
2-5.不当解雇に関する相談
正当な理由なく一方的に解雇されるような事例です。
たとえば、労働者の勤務態度や資質・能力に問題があるとして解雇される場合や、会社の業績不振によりリストラされる場合があります。
前者の場合は勤務態度や成績の評価方法が、後者の場合はリストラ対象者の選定の合理性などがそれぞれ問題となるケースが少なくありません。
2-6.労働災害に関する相談
勤務中の事故やトラブルなどにより怪我や病気をし、または死亡してしまうような事例です。
職場の機械の誤操作による手の負傷や長時間労働による過労死など、様々なケースがあります。労災の場合は、労働基準監督署に対する労災申請のほかに、会社に対する損害賠償請求も検討すべきでしょう。
2-7.メンタルヘルスに関する相談
業務負荷や職場の人間関係などが原因でうつ病などのメンタルヘルス不調を発症するような事例です。
発症の代表的な原因としては、営業ノルマのプレッシャーやハラスメント被害、長時間労働などがあります。
労災が認められる場合もあるので、労働基準監督署などに積極的に相談しましょう。
2-8.退職(退職代行)に関する相談
不当な退職勧奨を受けたり、退職届が受理されないといった事例です。
具体例には、成績や勤務態度を理由に退職届の提出を強要される、代わりの人員が確保できるまで退職届の受取を拒否されるなどがあります。
会社からの引き止めが予想される場合、退職代行の業者を使うことも考えられます。
しかし、退職代行業者ではかえってトラブルになるケースもあるので、慎重に対応したい場合は弁護士に依頼するべきでしょう。
3.労働問題を電話・対面・オンラインで相談する場合のメリット・デメリット
3-1.電話相談のメリット・デメリット
電話相談のメリットとしては、すぐに回答を得られる、短時間で相談できるという点があります。
そのため、大まかな方向性だけでもいいから早く解決策を示してほしいという方にはおすすめです。また、忙しくてなかなか相談窓口に赴いて相談する時間がないという方にとっても有用でしょう。
他方で、デメリットとしては、時間に限りがある、資料や証拠を示して相談できないという点があります。
電話相談は時間に限りがありますので、相談員が相談内容を十分に理解できず、適切な回答を得られないおそれがあります。また、資料や証拠を示すことができないため、やはり相談者の側で相談内容を十分に伝えきれない可能性があるのです。
そのため、電話相談の際は、事前に相談内容を文章でまとめておき、相談員に相談内容を正確に伝えられるように準備しておきましょう。
3-2.対面相談のメリット・デメリット
対面相談におけるメリットは、正確に相談内容を伝えることができ、的確なアドバイスを受けられることでしょう。
対面相談では、相談員と同じ場においてリアルタイムでやりとりしながら相談ができるので、相談内容のニュアンスが正確に伝わりやすいです。
また、持参した証拠や資料を見ながら相談することもできるので、的確な回答が得られやすいという点もあります。
相談内容が複雑である場合や、方向性にとどまらず踏み込んだ回答がほしい場合は対面相談を利用する必要があるでしょう。
一方で、デメリットは、窓口が空いている時間帯が限られ相談できるタイミングが限定的である点です。
電話相談やオンライン相談でも解決できる簡単な相談以外は、土日も対応している窓口を利用してはいかがでしょうか。
3-3.オンライン相談のメリット・デメリット
オンライン相談には、メールやチャット、WEB会議などがあります。
(1)メール相談、チャット相談のメリット・デメリット
メールやチャットによる相談のメリットとしては、多くの場合24時間いつでも受け付けていることと、複雑な内容の相談でも文章で正確に伝えられることでしょう。
他方でデメリットは、双方向でのコミュニケーションではなく、一方的な情報の提供と相談から回答を受けるということになるため、的確な情報提供がなされていなかったり、聞きたいことが明確でない場合などには、回答してほしいことに回答されないという事態や回答にかかる時間が遅くなってしまうという事態が起こりがちという点です。
(2)WEB会議のメリット・デメリット
WEB会議では、窓口に出向く時間をかけずに、互いの表情を確認しながらコミュニケーションができます。
そのため、電話に比べて相談のニュアンスを伝えやすいというメリットがあります。
WEB会議のデメリットとしては、タイムラグがあるなど対面に比べるとコミュニケーションの質で劣る点と、事前の調整が必要なことが多く電話に比べて即時性に欠ける点です。
4.労働問題を相談する前に準備しておきたいこと
4-1.相談内容や質問をまとめておく
対面相談、電話相談、オンライン相談のいずれにおいても時間には限りがあります。
相談内容や質問をまとめておかないと、伝えたいことが伝えられず、聞きたいことも聞けずに相談時間が終わってしまうことになりかねません。
また、相談員から的確なアドバイスを得るためにも、相談者側からの説明がわかりやすいに越したことはないでしょう。
相談内容や質問を整理する際のポイントは以下の通りです。
- 登場人物(会社での肩書や相互の関係性など)
- いつ、誰が、どのようなトラブルを生じさせたか
- トラブルによってどのような被害が発生したか
- トラブルをどう解決したいか(解決してほしいか)
可能な限りで構いませんが、相談内容や質問を事前に整理しておいた方が自身の頭の中も整理できるため、準備しておくことをおすすめします。
4-2.関係資料を整理しておく
生じた労働問題に関する自身の主張を裏付けるための証拠や関係資料を事前に収集し、整理しておくこともまた重要になります。
証拠や資料があることで、相談員の相談内容についての理解が進みますし、どの程度の証拠があるかによって、解決に向けて取り得る手段が変わってくるからです。
証拠は相談内容によって異なりますが、たとえば残業代請求の場合は以下のような証拠があります。
【算定の基礎となる賃金や計算方法がわかる資料】
- 給与明細(源泉徴収票)
- 就業規則(賃金規程)の写し
- 雇用契約書(労働条件通知書)
【残業時間がわかる資料】
- タイムカード(その他各会社での勤怠管理の記録)
- 業務用パソコンのログ
- 家族への帰宅の連絡(LINE、メールなど)
また、ハラスメントでは一般的に証拠が残らないことが多いので、録音や記録につけるなどして、可能な範囲で積極的に証拠を収集していく姿勢が必要になります。
収集した証拠は、相談時にスムーズに取り出し、また示したい箇所を示せるように、事前に整理しておきましょう。
5.労働問題を解決するためには
5-1.行政機関の紛争解決手続を利用する
労働委員会や労働局のあっせん手続、労働基準監督署への通報といった手段があります。
あっせん手続では、労働問題の専門家によるあっせん案の提示が受けられますし、労働基準監督署が動けば実際に問題が解決することもあるでしょう。
しかし、行政機関によるあっせん案には強制力がなく、労働基準監督署はすべての案件に対応してくるわけではありません。
そのため、会社の任意の協力によらず自らの権利を実現するには、裁判手続の利用が必要になるのです。
5-2.訴訟などの裁判手続を利用する
労働問題を解決するための主な裁判手続としては、労働審判、仮処分、訴訟があります。
労働審判は、裁判所で行われている迅速かつ専門性の高い紛争解決制度です。
審理が原則として3回以内で終わるため、67.6%の案件が申立てから3ヶ月以内に終了しており、迅速な解決が図られています。
また、裁判官である労働審判官一名と労働実務の知識、経験豊富な労働審判員二名により対応しますので、専門家による労働実務に即した紛争解決が期待できるでしょう。
参考:労働審判手続
仮処分は、訴訟による請求を待っていては労働者の権利保護に不十分である場合に、裁判所の決定により暫定的に権利利益を認める制度です。
たとえば、解雇された場合に、勝訴により復職するまでの期間について、労働契約上の地位を仮に認める仮処分や、賃金仮払いの仮処分を行います。
訴訟は、裁判所の判決によって、労働問題に限らずあらゆる法律問題を強制的に解決する制度です。
勝訴すれば強制執行ができるので紛争解決の実効性の点では最も優れていますが、他の手続きに比べて時間がかかります。
また、労働審判、仮処分、訴訟はいずれも専門的な知識や経験が必要となる手続きのため、弁護士に依頼するべきでしょう。
5-3.弁護士に依頼する
弁護士に会社との交渉や裁判手続の対応を依頼する方法です。
費用はかかりますが、専門家である弁護士に交渉を依頼することで会社の対応が変わることもありますし、裁判手続は本人一人での対応がそもそも難しいと言わざるを得ません。
詳しくは後述しますが、弁護士に依頼すれば、交渉などによる労力や時間を趣味などの有用な時間に充てることができます。
5-4.転職する
今の職場から離れたい、離れても良いという方にとっては、転職が大きな選択肢になるでしょう。
行政機関にせよ弁護士にせよ、相談するとなれば時間がかかります。裁判制度の利用や弁護士への依頼となれば費用も必要です。
特に、意図的に労働法令に違反する会社に勤めていても明るい未来はありませんから、時間や費用をかけて争うよりも、早期に転職した方がよい場合もあるでしょう。
6.労働問題を弁護士に依頼するメリット
労働問題を解決するための対応を弁護士に依頼する主なメリットは以下の3つです。
6-1.的確な解決策を示してくれる
弁護士は法律の専門家であると同時に紛争解決のプロです。
事実関係と自身の言い分を伝えれば、会社に対して法律上どのような権利、利益を主張できるのか、またどのような解決方法があるのかを示してくれます。
本人一人で対応していると、見通しがわからず途中で不安になってしまうことも少なくないでしょう。
弁護士に依頼すれば、解決の見通しについてわかりやすく説明してくれるので、安心して結果を待てるのです。
6-2.労働者の立場に立ち親身に相談を受けてくれる
弁護士は相談した労働者に寄り添い、親身になって対応します。
行政機関は基本的に公正中立な立場であるため、どうしても客観的な立場での対応になりがちです。
弁護士であれば、相談者の立場、視点に立って悩み相談を聞いてくれたり、親身になって一緒に解決策を考えてくれたりします。
また、弁護士は法律上の守秘義務を負っているため、相談内容を他言される心配がありません。
そのため、たとえばセクハラ被害のような家族や友人にも話しにくいセンシティブな内容であっても、安心して相談できるのです。
訴訟になれば、解決までに時間がかかることも少なくありません。
労働トラブルが解決するまでの長い間、労働者に寄り添い親身になって何でも相談に乗ってくれる弁護士の存在は、大きいといえるでしょう。
6-3.トラブル解決のための交渉などを代わりに行ってくれる
弁護士に依頼すれば、会社との交渉や、訴訟などの手続きを代わりに行ってくれます。
会社を相手にして、一人で交渉するにはたくさんの時間と労力が必要です。
たとえば、自身の言い分を法律上の主張として整理するためには、労働関係の専門的な法律を調べて理解することが必要になるでしょう。
弁護士に依頼する場合は、自身の言い分を伝えておけば、後の作業は法律のプロである弁護士が的確に行ってくれるため、時間や労力をかけずに済むのです。
また、訴訟や労働審判といった裁判手続に関しては、より高い専門知識と実務経験が求められますので、そもそも本人一人で行うこと自体困難です。
労働問題について会社との交渉や裁判手続を代理できる専門家は弁護士のみですので、他の相談窓口などにはない大きなメリットといえるでしょう。
なお、依頼する際は、HPなどから労働者側の立場で労働問題を専門的に扱っている弁護士事務所を探すと良いでしょう。
労働問題を解決するための十分な対応には、実務経験が欠かせないからです。
7.まとめ
労働問題に関するトラブルには様々な種類がありますが、共通しているのは、解決のために一人で対応しようとすると多大な手間と時間がかかるということです。
行政機関などの労働問題の専門的な相談窓口を利用した場合でも、最後は自身で対応する必要がありますので、手間暇がかかるという点は同じでしょう。
労働問題の対応に手間暇をかけたくないという方は、弁護士に相談し、対応を依頼してみてはいかがでしょうか。
費用はかかりますが、トラブル解決のための対応を一任でき、浮いた時間を趣味や自分の好きなことに充てられます。
この点、当事務所であれば初回の相談料(60分間)は無料であり、費用の心配なくご相談いただけます。また、対面相談のみならず、電話、メール、LINE、WEB面談の方法でも相談を受け付けており、お気軽にお問い合わせいただけます。
私たち法律事務所リーガルスマートは、労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
担当者
-150x150.png)
- 法律事務所リーガルスマート弁護士
-
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
担当記事
 不当解雇2月 28, 2024突然の解雇されたらどうなる?手当や対処法を弁護士が解説!
不当解雇2月 28, 2024突然の解雇されたらどうなる?手当や対処法を弁護士が解説! 不当解雇2月 16, 2024無断欠勤は解雇になる?解雇される欠勤日数などを弁護士が解説!
不当解雇2月 16, 2024無断欠勤は解雇になる?解雇される欠勤日数などを弁護士が解説! その他2月 16, 2024確実に退職できるやむを得ない理由とは?具体例を弁護士が解説!
その他2月 16, 2024確実に退職できるやむを得ない理由とは?具体例を弁護士が解説! その他2月 5, 2024非正規雇用とは正規雇用との違いや課題点などを弁護士が解説!
その他2月 5, 2024非正規雇用とは正規雇用との違いや課題点などを弁護士が解説!